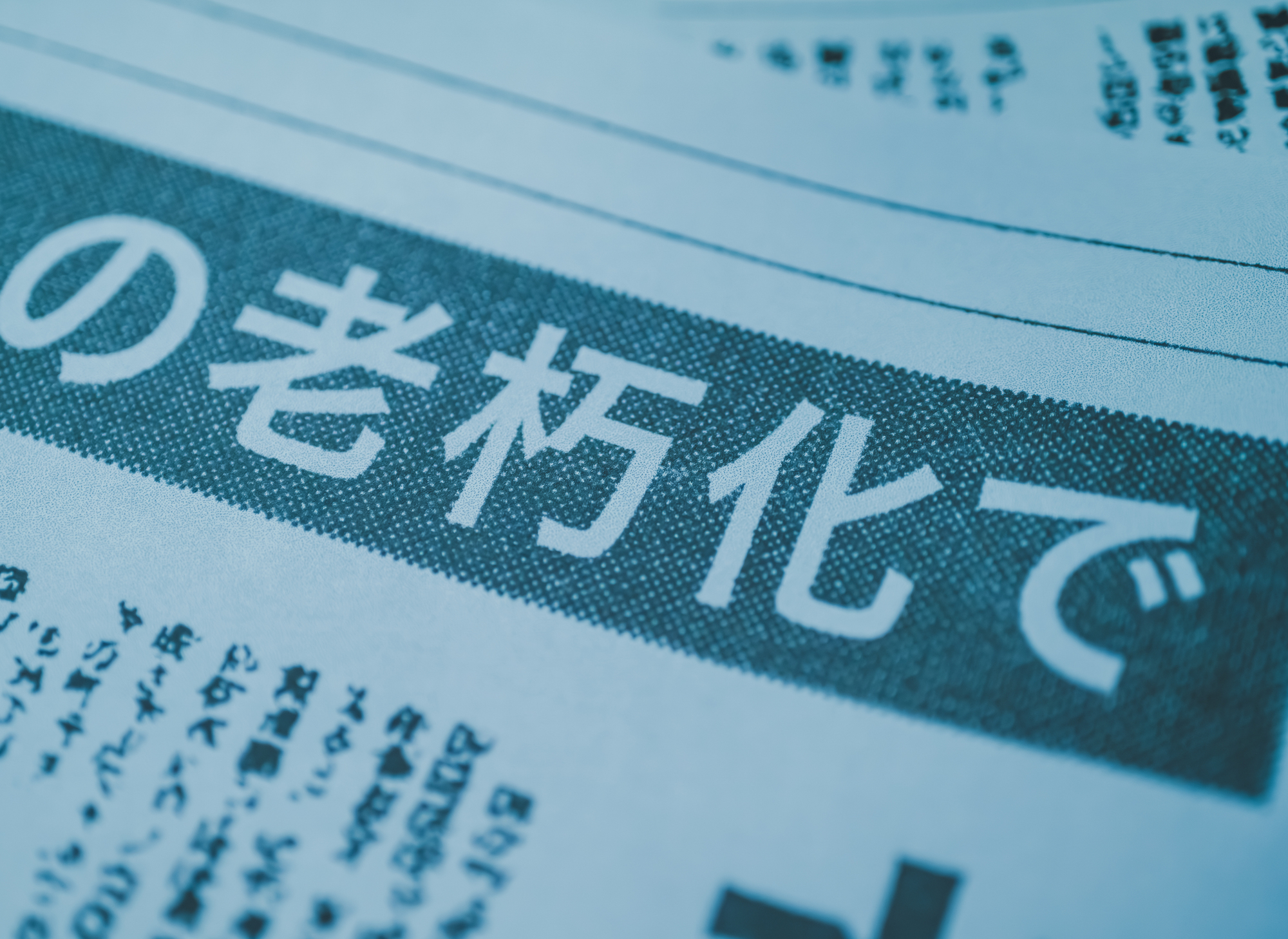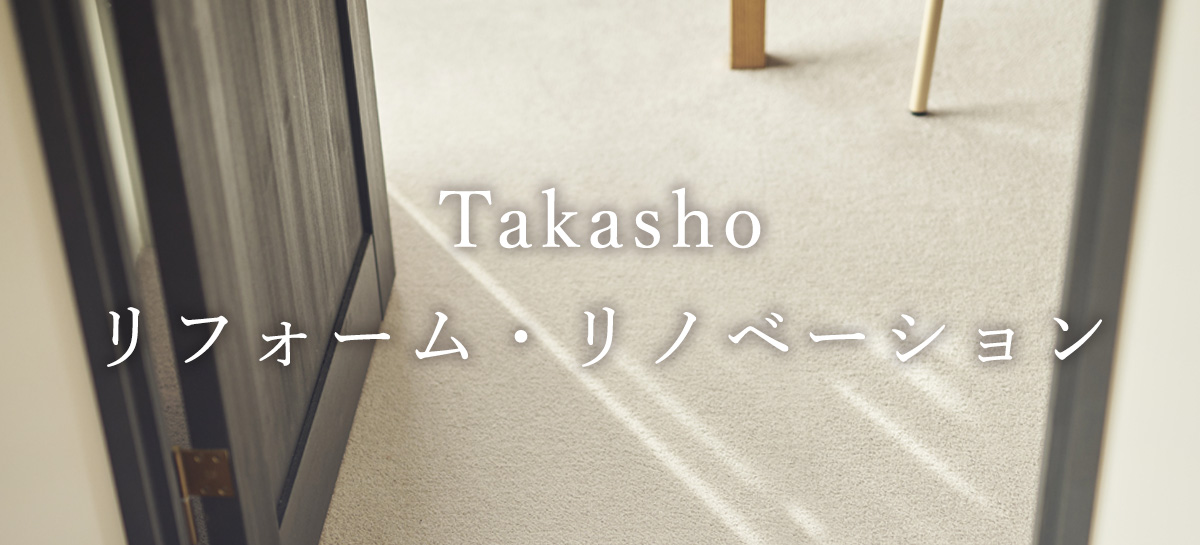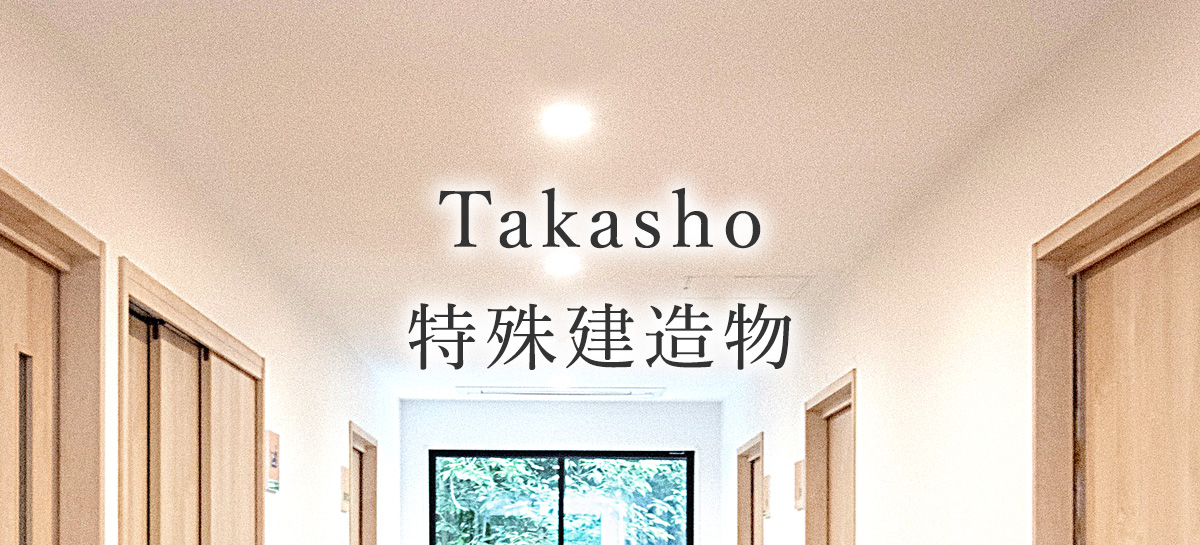不動産を所有したり、投資対象として運用すると、税金対策になるということを聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。しかし、どのような仕組みで税金対策ができるのか疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。そこで、この記事では不動産投資で節税できる税金の種類や、節税を考えるうえで注意したいポイントなどをご紹介します。将来的な資産形成のために不動産投資やマンション経営を検討している方はぜひ最後までご覧ください。
この記事を読むとわかること
- ・「損益通算」と「減価償却」を活用し、不動産投資で所得税・住民税を減らす具体的な仕組みが理解できる
・高所得者ほど節税効果が高まる「累進課税」との関係や、キャッシュフロー改善のメリットがわかる
・節税対策において、減価償却費を大きく計上できる「築古木造物件」が有利な理由を把握できる
・管理費や修繕費、ローン利息など、確定申告で「経費」として計上できる項目と注意点がわかる
・節税目的の投資に伴う赤字リスクや、売却時の税金(譲渡所得税)まで考慮した出口戦略の重要性が学べる
目次
不動産投資による節税の基本

不動産投資が税金対策につながる理由はいくつか存在します。詳しく解説します。
不動産投資で節税できる仕組み
不動産投資には、税金を軽減できる仕組みが組み込まれており、高所得者にとって効率的な節税手法となります。その仕組みの一部には、不動産所得の赤字を他の所得と損益通算し、課税所得を圧縮するものや、減価償却費を計上して課税対象額を削減するものがあります。このような税制上の特典を活用することで、所得税や住民税の負担を軽減し、キャッシュフローを向上させることが可能です。さらに、不動産投資の魅力は節税だけではありません。将来的に不動産価値が上昇した場合、収益の拡大が見込めるため、資産形成においても有力な選択肢といえます。特に年収が高い場合、節税効果が大きくなるため不動産投資がさらに魅力的になります。例えば、年間500万円以上の税金還付を受けた事例があり、こうした最高効率を目指した投資プランは高所得者を中心に注目されています。
減価償却と損益通算を活用した節税方法
不動産投資で大きな節税効果を得るためには、減価償却と損益通算の活用がポイントになります。減価償却とは、不動産の建物部分にかかる費用を経年にわたって分割して経費計上することで、課税対象所得を効果的に圧縮する方法です。築古の木造物件では減価償却費を多く計上することが可能で、これにより大幅な節税が期待できます。また、不動産所得が赤字となった場合、損益通算の制度を利用して、その赤字を給与所得など他の所得と相殺することができます。
例えば、購入初年度に減価償却費を多く計上することで赤字が発生する場合がありますが、この損益通算を通じて所得税の還付を受けることが可能です。この仕組みを最大限に活用することで、短期的には税金還付によるキャッシュフローの改善を、長期的には資産形成と節税の両立を目指すことができます。
所得税・住民税の軽減効果
不動産投資による節税は、特に所得税や住民税の軽減において大きな効果を発揮します。税制上、不動産収入から発生する経費や減価償却費を計上することで、不動産所得の課税額を引き下げることが可能です。この結果、総所得が圧縮され、その分の所得税と住民税が軽減されます。特に所得税や住民税が累進課税に基づいて課される日本では、課税対象額が高いほどその削減効果は顕著になります。
例えば、年収1,000万円以上の高所得者の場合、不動産投資を通じて年間で数百万円単位での税金還付を受ける可能性があります。これにより、節税効果を享受しつつ余剰資金で次の投資物件やライフプランに充てることも可能です。ただし、所得税や住民税率がそれほど高くない場合、節税効果が限定的になるため不動産投資が必ずしも適しているとは限らない点を考慮する必要があります。
相続税・贈与税への節税効果も知っておこう
不動産投資は、所得税や住民税だけでなく、相続税や贈与税における節税対策としても有効です。不動産を資産として保有している場合、その評価額は固定資産税評価額や相続税評価額が適用され、現金資産と比較して評価額が低くなります。このため、相続時に課税対象となる財産額を圧縮でき、結果的に相続税が軽減される仕組みです。
さらに、不動産を早めに贈与することで、贈与税の負担を分割しながら資産を次世代に移転することも可能です。特に、不動産投資を通じて築古物件の購入や管理を行う場合、評価額の圧縮と減価償却による節税効果の相乗的なメリットがあります。ただし、相続や贈与には特有の法律や税制が絡むため、事前に税理士など専門家と相談のうえで進めることが重要です。
不動産投資で節税する際の具体的な方法
物件購入時に考えるべき節税ポイント
不動産投資で節税を成功させるためには、物件購入時にいくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。まず、物件の種類によって節税効果が大きく異なるため、「木造」「築古」の物件を選ぶことが推奨されます。木造物件は減価償却費を大きく計上できるため、課税所得を大幅に圧縮できるメリットがあります。また、築古物件の場合、購入価格全体のうち土地ではなく建物部分の価値が高くなる傾向があり、減価償却費用をさらに拡大させることが可能です。ただし、節税を目的とした新築物件の購入には注意が必要です。新築物件は建物価値に対して減価償却費が少ないため、節税効果を十分に得ることができません。また、購入時のローンや自己資金とのバランスも重要です。過度な借入はリスクを高めるため、収益を見込めるバランスの取れた資金計画を立てましょう。
経費として申告可能
不動産投資による節税では、各種費用を経費として申告することで課税所得を下げることが可能です。例えば、物件の管理費や修繕費、固定資産税、火災保険料などは経費として計上できます。また、物件購入に伴う不動産取得税や登記費用も、経費に含めることが認められます。
さらに、収益物件を維持・運営するための交通費や通信費、税理士への相談費用なども経費として申告可能です。ただし、これらの経費は適正に記録し、その使途を明確にしておく必要があります。適切な経費申告を行うことで、節税効果を効果的に得ることができるでしょう。
確定申告で押さえておきたい節税テクニック
不動産投資で節税を実現するためには、確定申告を正確に行うことが重要です。まず、前述のように計上可能な経費を漏れなく申告することが大事です。その際、領収書や契約書などの証拠書類を整理し、不備がないように管理しておきましょう。また、赤字となった不動産所得については、他の所得との損益通算を活用することが可能です。例えば、不動産所得が赤字の場合でも給与所得がある場合は、その赤字額を給与所得から差し引くことで所得税や住民税を軽減できます。ただし、この赤字部分が実質的に投資リスクを伴うことにも注意が必要です。
確定申告時には、専門的な知識が必要になる場合も多いため、税理士や専門家のアドバイスを活用するとさらに円滑に手続きを進められます。
節税対策に効果的なローンの使い方
不動産投資で節税効果を最大化するためには、ローンを上手に活用することが鍵となります。不動産ローンを利用することで、支払利息を経費として計上することが可能です。その結果、課税所得を圧縮し、節税効果を得ることができます。
特に、短期で減価償却が進む築古物件とローンの組み合わせは節税効果が高いとされています。しかし、ローン活用には注意が必要で、過剰な借入は返済リスクを高める可能性があります。そのため、収益と返済額のバランスを考慮しながら、無理のない計画を立てることが重要です。資金計画を立案する際は、長期的な収益と減価償却費の推移も考慮すると良いでしょう。
節税を目的とした投資のリスク

節税を重視しすぎた場合のデメリット
不動産投資を節税目的で行う場合、収益性を軽視するリスクがあります。多くの物件で、「節税になる」というセールストークを鵜呑みにしてしまうと、実際には取得した不動産が赤字を生み続け、最終的に投資として成り立たなくなるケースも少なくありません。また、節税効果ばかりを優先して購入した物件が運用上の手間や修繕費などで予想以上にコストがかかり、結果的に資産を増やす目的が達成できなくなる可能性もあります。不動産投資で節税を目指す際には、収益性と税効果のバランスを慎重に検討することが大切です。
税制の変動によるリスク
不動産投資による節税効果は、税制が現在のままであることを前提としています。しかし、税制は政府の財政や経済政策に応じて頻繁に変動する可能性があります。たとえば、減価償却制度の変更や損益通算の制限など、不動産投資に有利な税制が改正された場合、期待していた節税効果が得られなくなる可能性が考えられます。また、所得税率や住民税率の引き上げが行われた場合、高所得層向けの節税策として魅力的だった仕組みが薄れることもあり得ますので、税制の今後の動向にも注意を払いましょう。
物件売却時に気をつけたいポイント
不動産投資で課税所得を圧縮し、節税に成功したとしても、物件売却時には注意が必要です。高額で売却した場合や資産価値が大幅に上昇した物件を売る際には、譲渡所得税が発生する可能性があります。この税負担が予想よりも大きくなると、それまでの節税効果が帳消しになることもあります。特に、短期間での売却は長期譲渡よりも高い税率が適用されるため、売却タイミングを慎重に見極めることが重要です。さらに、築古物件では減価償却が進み資産価値が低下しやすいため、売却時の価格が購入価格より大幅に下がるリスクも頭に入れておく必要があります。
節税目的で赤字を続けるリスク
不動産投資では、節税効果が期待できるからといって赤字経営を続けることは大きなリスクとなります。初年度や購入直後は経費や減価償却費を活用して課税所得を抑えられる場合がありますが、長期的に赤字が解消しない場合、自己資金を圧迫し、キャッシュフローを悪化させる可能性が高まります。さらに、収益性のない物件を維持し続けると、不測の修繕費や災害リスクによる追加経費が発生することもあります。節税はあくまでも副次的なメリットであり、投資対象物件そのものの収益性や長期的な価値向上を重視することが、安定した不動産投資の鍵となります。
成功する不動産投資での節税のコツ
節税効果と収益性の両立を目指す投資プランを立てる
不動産投資による節税を成功させるためには、節税効果だけでなく、収益性もしっかりと考慮した投資プランを立てることが重要です。節税を狙うあまり、赤字の多い物件や収益性の低い物件に手を出してしまうと、長期的には資産減少につながる可能性があります。特に収入が高い人ほど節税メリットを享受できるため、高所得者向けの物件選びがカギとなります。具体的には、減価償却効果が大きい築古の木造物件や、一棟収益物件が適した選択肢といえるでしょう。
税理士や専門家のアドバイスを取り入れる
不動産投資で効果的な節税を実現するためには、専門家である税理士のアドバイスを活用することをおすすめします。不動産投資には、減価償却や損益通算など、税務上の複雑な処理が伴います。このため、税理士など専門家をパートナーにすることで、最新の税制を反映した最適な節税プランを立てることが可能です。また、確定申告においても、正確で漏れのない手続きができるため、余分な税金を払うリスクを避けることができます。
長期的な効果を見据えた節税戦略を描く
不動産投資の節税は、短期的な利便性だけに目を向けるのではなく、長期的な視点を持つことが大切です。例えば、最初の数年間は減価償却を活用して節税効果を得られる一方で、築年数が進むにつれて減価償却費が小さくなり、課税所得が増加することもあります。そのため、家賃収入や将来の物件売却時の利益を含む全体の収益計画を立て、あくまでもトータルでメリットを得る戦略を練ることが重要です。税金還付のシミュレーションを行うなどして、節税対策と資産運用のバランスを取った投資を目指しましょう。
まとめ | 税金対策だけに気を取られず、不動産投資を始めてみませんか?

不動産投資を行うことによる税金対策について、詳しく解説してきました。何度か触れてきたように、不動産投資により、耐用年数以内であれば所得税や住民税の金額を大きく抑えられるほか、財産の贈与や相続を行う際の納税額を軽減できます。逆にいえば、減価償却を計上できる期間を超えると、節税効果が薄くなってしまうため、不動産投資を始める際は、いつ売却するかまでをも考えて計画を立てることが大切です。また、減価償却を行うことにより、物件の購入費用を経費として一定期間申告できますが、投資用ローンや修繕費といったそのほかの必要経費は自己負担となります。そのため、安易に不動産投資を始めてしまうと、経費の支出が多過ぎてしまい、事実上赤字となってしまう恐れもあるため、注意が必要です。このように、不動産投資には、そのほかの投資と同様、メリットだけではなくリスクも存在します。リスクも十分に考慮したうえで、手持ちの資金に余裕がある状態で不動産投資を始めるように心がけましょう。
高翔では、物件選びや運営のポイントなど不動産投資を始めるにあたっての疑問点や不安を解消するための無料相談を受け付けております。豊富な実績をもとに幅広い物件の紹介や、賃貸運営のサポートを行っていますので、不動産投資を検討している方は、ぜひ利用してみてください。