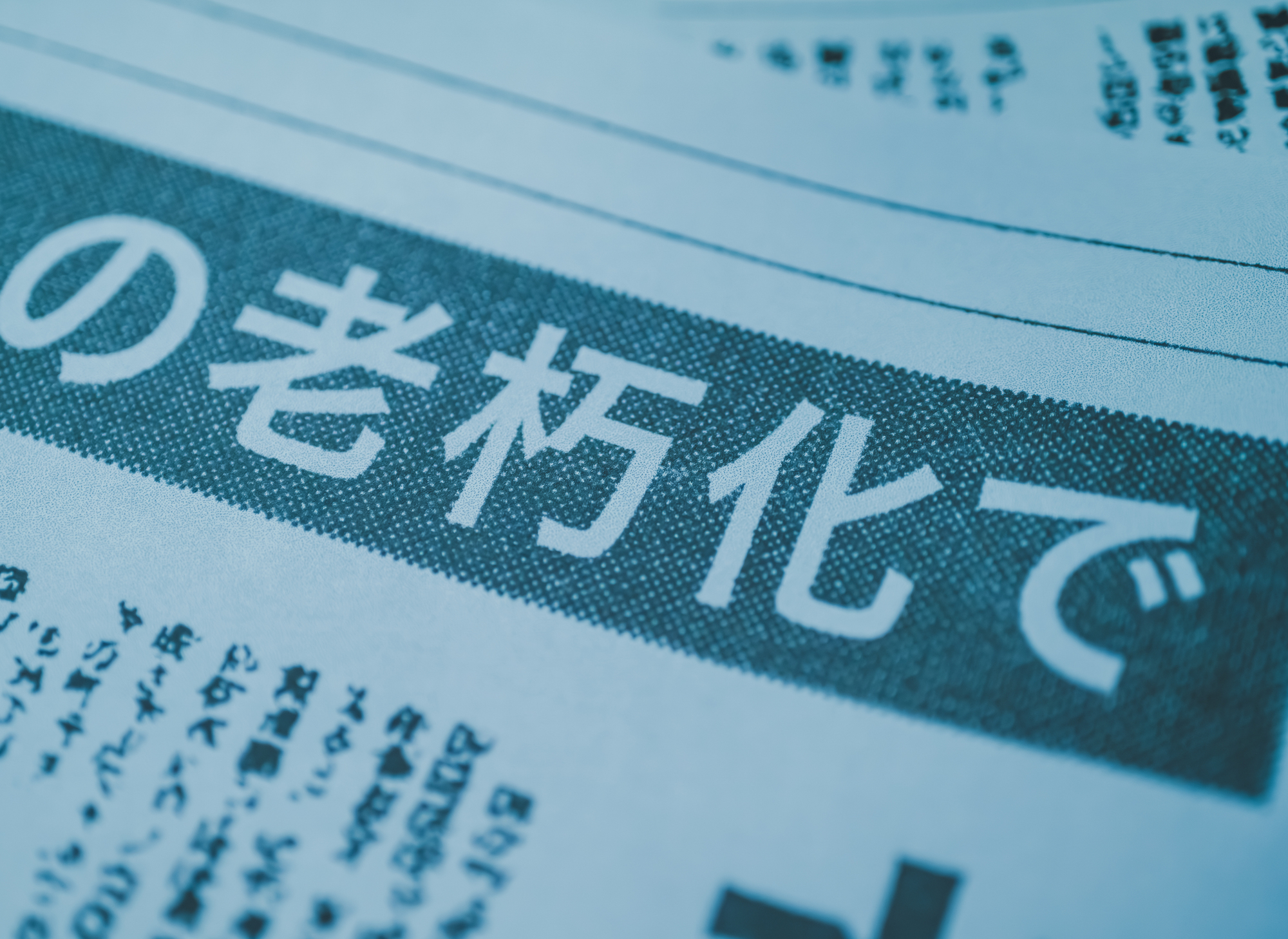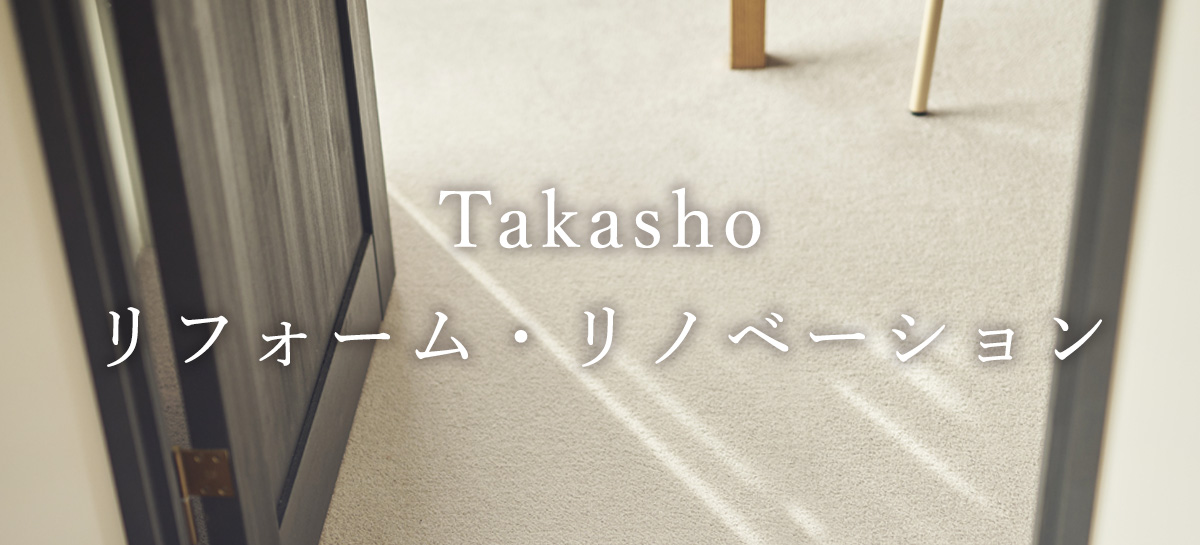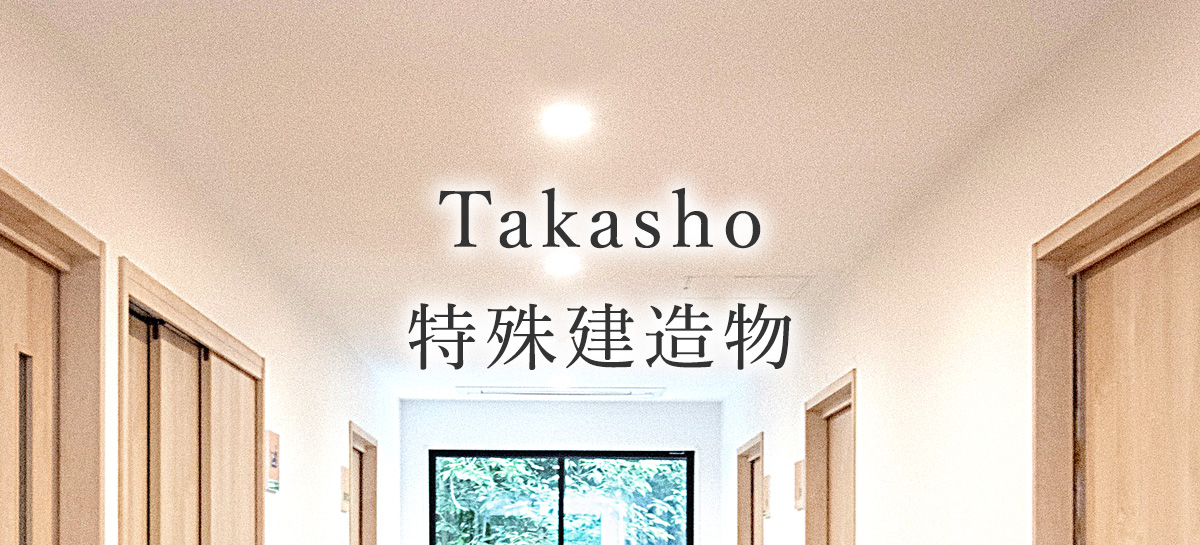相続税の負担を大きく減らす節税として知られているものの一つに、不動産を活用する方法があります。不動産を購入することで節税できるのは、不動産が取引される時価(実勢価格)と相続税がかかる基準となる価格(相続税評価額)に大きな差があるためです。適切な相続税対策ができるよう、不動産に関する相続税の仕組みを知り、どのように節税できるのかを具体的な方法も含めて解説します。ぜひ最後までご覧ください。
この記事を読むとわかること
- ・現金を不動産に換えることで、相続税評価額を時価の2~3割圧縮できる仕組みがわかる
・「小規模宅地等の特例」や借入金を活用した、具体的な節税方法が理解できる
・不動産特有の「分割しにくさ」や「換金性の低さ」といったデメリットを把握できる
・節税目的とみなされた場合の「否認リスク」や、購入後の維持コストについて学べる
不動産投資を相続税対策にするメリット
現金から不動産への資産変換で評価額を減少できる
不動産投資は、相続税対策として現金を不動産へ変換することで、資産の評価額を減少させる効果があります。現金や預貯金は相続税の評価額がそのままの金額で計上されますが、不動産は路線価や固定資産税評価額を基に評価されるため、実際の市場価値よりも低く算出されます。たとえば、1億円の現金を土地や建物に投資すると、相続税評価額は通常7,000万円から8,000万円程度に抑えられることが多く、約20〜30%の評価額減少が期待できます。この評価減少が大きな節税効果を生む理由の一つです。
建物の建設で相続税評価額を減少できる
相続財産に更地がある場合は、その土地にアパートやマンションを建てることで貸家建付地となり、相続税評価額が下がります。
貸家建付地の相続税評価額は以下のように算出します。
貸家建付地の評価額=更地の評価額-更地の評価額×借地権割合×借家割合×賃貸割合
小規模宅地等の特例による大幅な減額効果がある
小規模宅地等の特例は、不動産を相続する際に非常に大きな節税効果をもたらす制度です。たとえば、被相続人が住んでいた宅地の場合、一定の条件を満たせば土地の相続税評価額を最大80%減額できます。また、賃貸用不動産であれば、貸付事業用宅地等として50%の減額を受けられるケースもあります。この特例を適用することで、不動産の相続税評価額をさらに引き下げることができ、相続人の税負担を大幅に軽減できます。ただし、適用条件や範囲は詳細な確認が必要であり、専門家への相談が必要になることが多いでしょう。
具体的な不動産投資の節税方法
借入を活用することでの相続財産減額
不動産投資を行う際、金融機関から融資を受けると借入金が相続税の課税対象となる財産総額から控除されます。借入を活用することで実際の資産価値の減額が可能となるため、相続税対策として非常に効果的です。例えば、1億円の収益物件を全額借入で購入した場合、その物件の相続税評価額や将来的な収益は資産として計上されますが、同時に借入という負債が相殺される形になるため、課税対象となる財産の総額が減少します。ただし、無理な借入は後々の返済負担やリスクを引き起こすため、計画的な借入計画が必要です。
生前贈与と不動産活用の組み合わせ
生前贈与と不動産投資を組み合わせることも相続税対策として効果的です。生前贈与は、贈与税の非課税枠を活用して、一定額を毎年非課税で次世代へ移転することが可能です。この仕組みを利用して、不動産を活用したい場合には、先に現金を非課税贈与し、それを元手に収益物件を購入してもらう方法があります。収益物件を次世代が購入する形を取れば、将来的な資産の分散が図られ、相続時における税負担が軽減されます。また、不動産を直接贈与する場合もありますが、この場合は不動産の相続税評価額が市場価値より低いことが多いため、税負担を抑える効果が生じます。ただし、贈与後3年以内の相続では注意が必要で、この場合は贈与財産が再び相続財産に加算されるため、計画的な実行が求められます。
不動産を活用した相続対策のデメリット
不動産の取得と維持には諸経費が発生する
不動産を活用した相続対策を行う場合、取得時と保有時にそれぞれ諸経費がかかります。
<不動産取得時にかかる諸経費の例>
・物件の取得費用(現金購入の場合)
・金融機関への事務手数料や保証料など(ローンを利用する場合)
・不動産取得税登記費用(登録免許税・司法書士報酬)
・不動産会社に支払う仲介手数料
<不動産保有時にかかる諸経費の例>
・管理費・修繕積立金(マンションの場合)
・外壁や屋根などの修繕費用(戸建ての場合)
・ローンの返済費や利息負担(ローンを利用する場合)
・管理委託料(管理会社に管理を委託する場合)
・固定資産税都市計画税(不動産が市街化調整区域にある場合)
・損害保険料(火災保険料・地震保険料)
また、相続人が不動産を売却するときも、手数料や税金などの諸費用がかかります。相続対策のために不動産を取得したとしても、支払うコストが高いと保有財産を減らしてしまうかもしれません。また、不動産を相続した人の金銭的な負担も重くなる恐れがあります。不動産で相続対策をするときは、取得時や保有時に支払うコストも踏まえて、慎重に資金計画を立てることが重要となります。
現物の不動産は分割がしにくい
被相続人が遺言書を残していない場合、相続人同士で遺産分割協議をして、誰がどの遺産をいくら相続するのかを決めます。現金であれば、法定相続分に応じ分けることで、相続人同士のトラブルは起こりにくくなるでしょう。しかし、不動産は現金とは異なり、分割がしにくい財産です。相続財産の大半が不動産であると、遺産を公平に分割するのが難しくなる可能性があります。
例えば、相続人が長男、長女、次男の3人だと、法定相続分は1/3ずつとなります。相続財産が2億4,000万円の場合、法定相続分に応じて分割すると、1人につき8,000万円ずつ相続できます。しかし、相続財産の内訳が2億円の不動産と4,000万円の現金であると、1人8,000万円ずつ分割するのが難しくなります。
不動産は換金スピードが遅く、換金性が低い
不動産は、現金、株式、投資信託などと比較すると換金性が低い財産です。例えば、預貯金であれば口座から引き出せば、すぐに現金を手にできます。また、株式や投資信託などの金融商品であれば、証券会社に売却の注文を出すと一般的に数日で現金化が可能です。しかし、不動産を現金化する場合、買主を見つけて売買契約を結ばなければなりません。また、不動産を売却する際は買主探しを不動産会社に依頼するのが一般的であるため、現金化までに時間がかかります。買い手探しが難航すると、現金化までに半年〜1年以上かかることもあります。相続対策とはいえ、買い手がなかなか見つからないような不動産を相続してしまうと、かえって相続人の負担が増える場合があります。また、相続財産の大部分が不動産であると、相続税の納税資金を準備できなくなるリスクが高まります。相続税の申告・納税の期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)から10ヶ月です。相続税は現金で納めるのが原則であるため、不動産が思うように売れないと納税資金が不足する恐れがあります。
不動産による相続税対策を行う際の注意点
明らかに節税を目的に不動産を購入しない
不動産の購入目的が明らかな相続税の節税であると判断されると、税務署から否認される可能性があります。 税務署から否認されると、路線価方式ではなく時価で相続税評価額を算出することになるため、相続税の負担は増えてしまいます。また、過少申告加算税や延滞税といったペナルティも課せられてしまいかねません。 税務署が、あからさまな相続税の節税と判断する基準を、明確に設けているわけではありませんが、相続対策のために不動産を購入する場合は、「事業や居住など節税以外の目的を明確にしておく」「相続した不動産をすぐに売却しないようにする」などの方法で対策をすることが大切です。 また、相続対策に詳しい不動産会社や税理士にも相談するのがおすすめです。
不動産を取得したあとの維持・管理
相続対策として不動産を取得したあとは、資産価値を落とさないために、建物や設備などを適切に維持・管理する必要があります。そのため、適切な方法で不動産を管理していくことが大切です。不動産の管理を個人で行う(自主管理)場合、時間と労力がかかります。自主管理が難しい場合は、管理会社へ管理業務を委託(管理委託)しましょう。ただし、自主管理と管理委託それぞれに、メリットデメリットが存在します。両者を比較検討し、自身に合った管理方法を選びましょう。
専門家に相談しながら適切な相続税対策を

相続税対策を成功させるためには、まず家族との話し合いが重要です。不動産投資による節税を検討する場合、相続する側とされる側の意向を事前に確認しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。また、不動産投資や金融の専門家、税理士などのプロに相談することで、税金や法律に関する最新情報を的確に把握することができます。プロの助言を受けながら適切な計画を立てることは、相続税対策を成功に導く鍵となります。
高翔では、物件選びや運営のポイントなど不動産投資を始めるにあたっての疑問点や不安を解消するための無料相談を受け付けております。豊富な実績をもとに幅広い物件の紹介や、賃貸運営のサポートも行っていますので、相続税対策のために不動産投資を検討している方はぜひ利用してみてください。