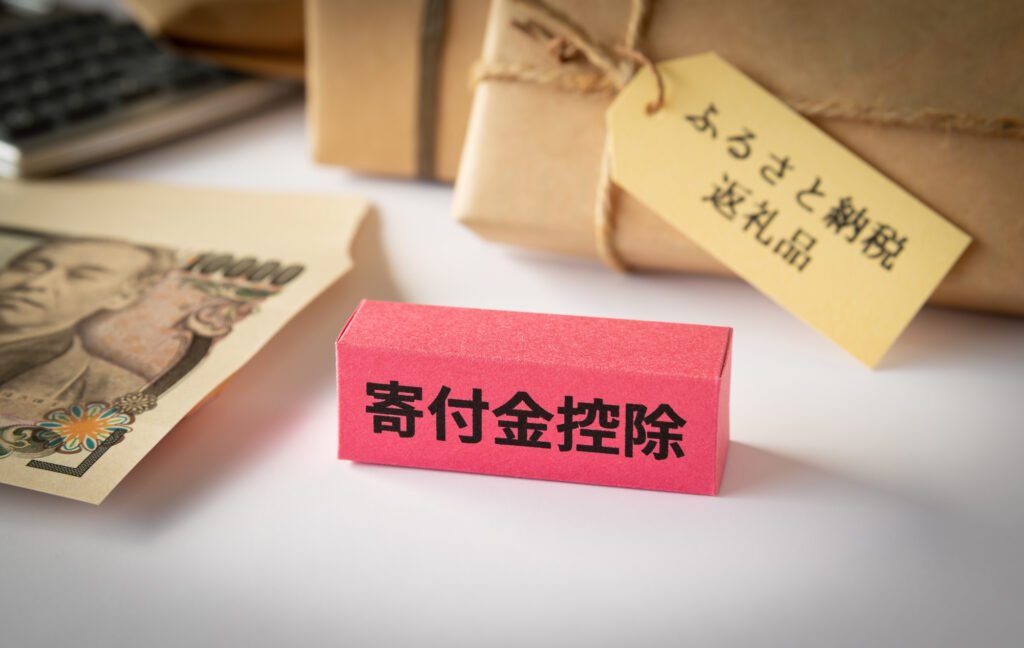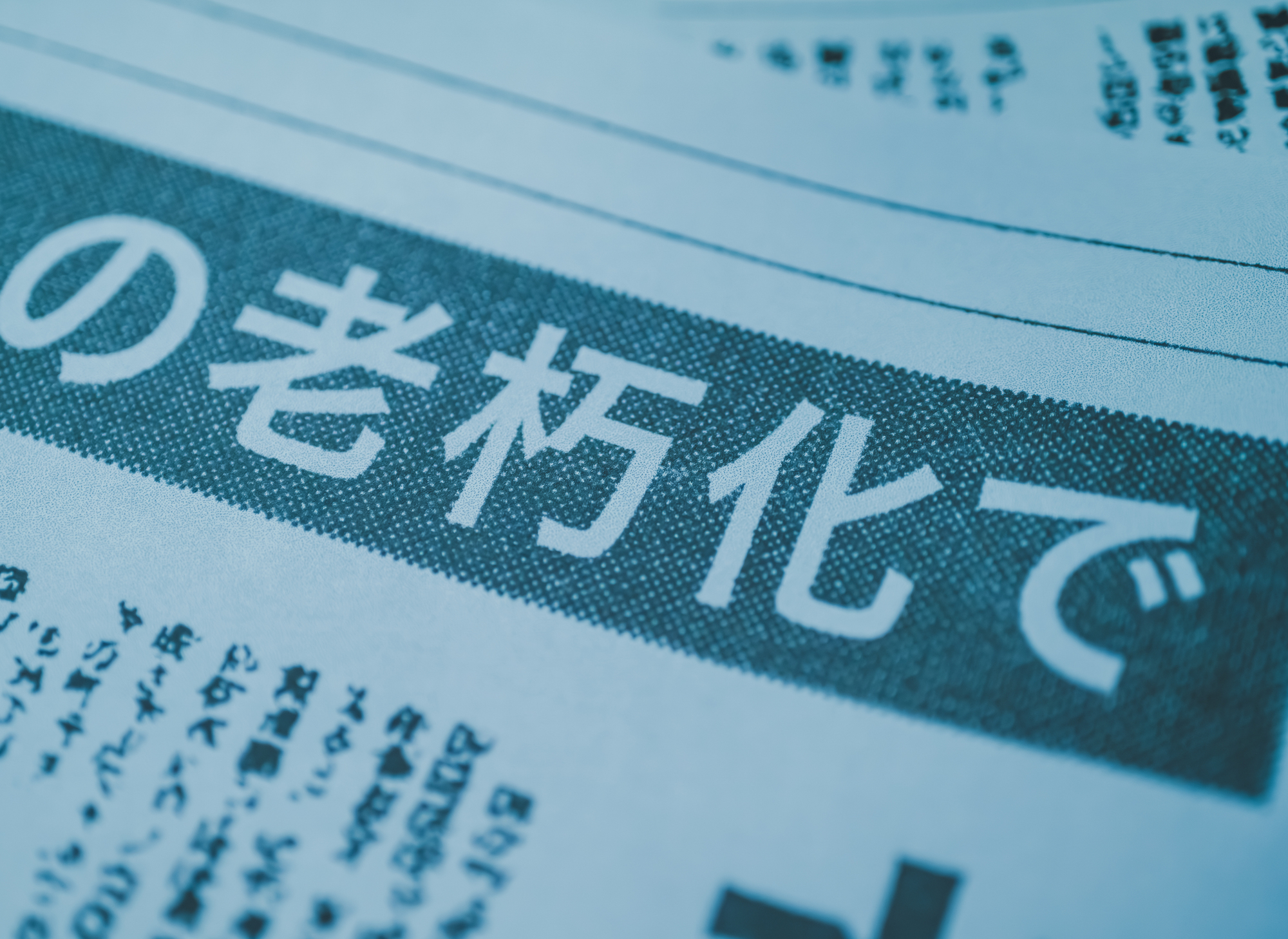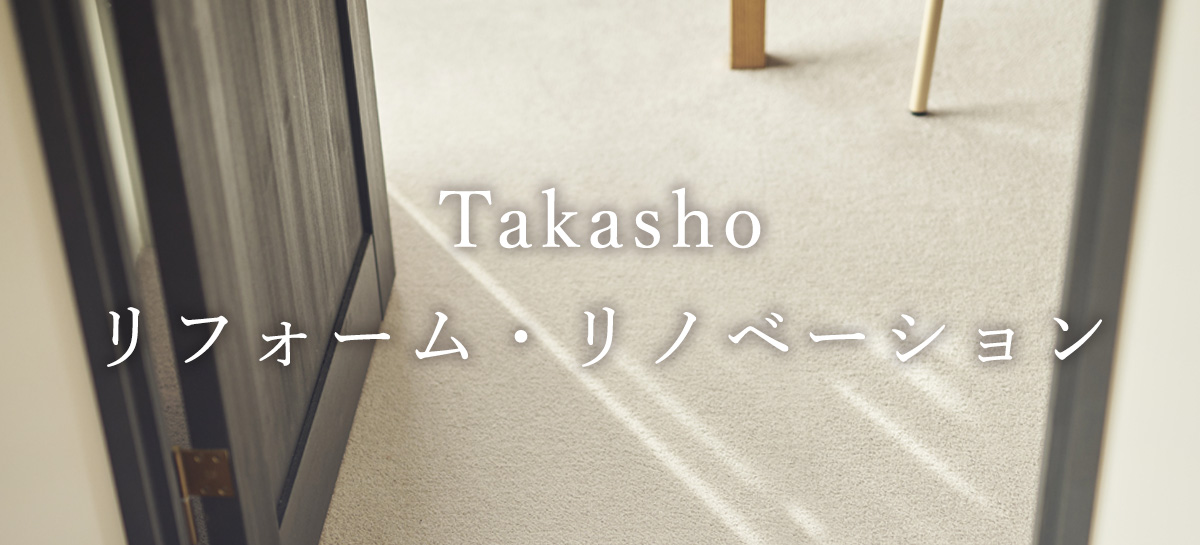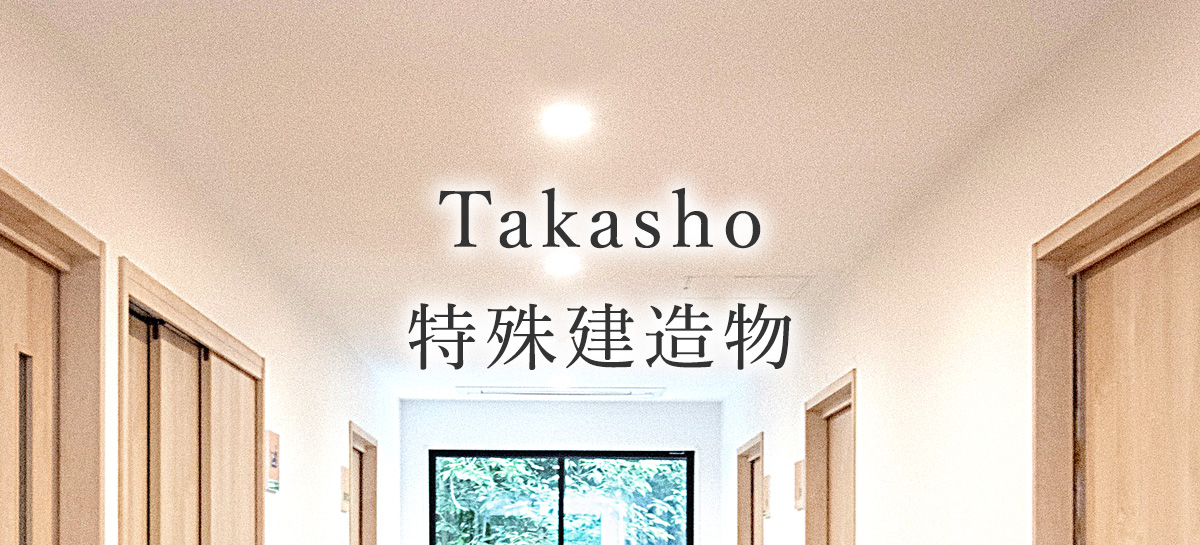個人に対する代表的な税金として、住民税があります。住民税は、給与所得者と個人事業主で納税方法が異なるほか、算出方法も所得税とは異なるため、住民税について「どのくらいの金額なのか」「いつ支払えばよいのか」などの疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。
収入が増えるにつれ、気になってくるのが税金です。特に住民税は「住民税決定通知書」で目にする機会もあり意識しやすいもののひとつと言えるでしょう。この記事では、住民税の基本的な概要のほか、所得税との違いや計算方法、支払時期などをわかりやすく解説いたします。住民税について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
この記事を読むとわかること
- ・住民税の仕組みや計算方法、所得税との違いが基礎から理解できる
・【年収別早見表】で、自分の住民税がいくらになるか目安を把握できる
・会社員と個人事業主で異なる「納付時期」や「納付方法」がわかる
住民税とは?

住民税とは、地域社会が提供する行政サービスのために、地域に住む人々が負担する地方税です。この税金は、具体的には「市町村民税」と「道府県民税」の二種類から構成され、それぞれ市区町村と都道府県で徴収されます。公共サービスの提供に必要な財源を地域住民が負担することで、道路や上下水道、学校教育、ゴミ処理といった身近なサービスが維持されています。また、住民税には「個人住民税」と「法人住民税」がありますが、ここでは住民一人一人に関わる「個人住民税」について解説いたします。
住民税と所得税の違い
住民税と所得税には、税率に違いがあります。所得税は、超過累進課税が採用されているため所得が高くなるほど税率が上がりますが、住民税は一律の税率(所得割10%)で計算されます。また、納税のタイミングも異なり、所得税は確定申告後に支払う仕組みなのに対し、住民税は前年の所得に基づき計算され、翌年6月から納付するのが一般的となっています。
住民税の構成:均等割と所得割
住民税は「均等割」と「所得割」という2つの構成要素で成り立っています。「均等割」は所得に関わらず定額で課せられる部分で、令和6年度から、兵庫県芦屋市の場合は、県民税1,800円、市民税3,000円の合計4,800円となっています。合わせて、令和6年度から森林の整備及び促進に関する施策の財源に充てるために創設された、森林環境税が創設され年額1,000円を国税として徴収されております。一方、「所得割」は前年の所得に基づいて課税されるもので、税率は一律10%(道府県民税4%、市町村民税6%)です。このように、一定額をすべての納税者が負担する均等割と、所得に応じた負担を求める所得割が組み合わさることで、公平性と安定性の両方を実現する仕組みになっています。
誰が住民税を支払う必要があるのか
住民税は、毎年1月1日現在で日本国内に住所を有している全ての個人に課されます。具体的には、市区町村に住民票を有している人が対象となります。また、一定の所得がある人が課税対象となるため、所得が非課税水準以下の場合には支払う必要がありません。さらに所得の状況に応じて、扶養控除や配偶者控除といった各種控除が適用される場合があります。なお、日本に住所を有する外国人であっても、同様に一定の所得がある場合は住民税の支払義務が生じます。
住民税の計算方法

住民税の計算方法について解説いたします。
課税所得の計算方法と控除の種類
住民税の計算で重要なのは課税所得額です。課税所得額は、前年の収入から給与所得控除を引いた「所得金額」から、さらに基礎控除などの「所得控除」を差し引いて算出されます。所得控除には医療費控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除などさまざまな種類があります。現行(令和8年度)の住民税における基礎控除は43万円です(合計所得金額が2,400万円以下の場合)。これにより、一定額以上の所得がなければ住民税が課されない場合もあります。また、これらの控除をしっかり活用することで住民税負担を軽減することができます。
住民税のシミュレーション例
住民税の負担額をイメージしやすくするため、シミュレーションを行います。たとえば、年間所得が300万円で、基礎控除43万円、社会保険料控除50万円、扶養控除33万円(住民税の一般扶養控除額)がある場合、まず年収300万円から給与所得控除(98万円)を引いた「給与所得」は202万円になります。そこから各種控除(合計126万円)を差し引くと、課税所得は76万円になります。76万円に対して所得割10%を課すと7万6,000円となり、これに芦屋市の場合の均等割4,800円と森林環境税1,000円を加えると、住民税の総額は8万1,800円となります。このように、控除をどれだけ活用できるかで住民税額が大きく変わることがわかります。
配偶者控除や扶養控除の影響
配偶者控除や扶養控除は、住民税の負担を減らす大きな要素です。たとえば、特定の条件を満たす配偶者がいる場合、最大33万円の配偶者控除(住民税の場合)を受けることができます。また、扶養するお子さまがいる場合、扶養控除が適用されるため、一人当たり33万円または45万円が控除されます。これらの控除を最大限に活用することで、住民税負担を大幅に軽減することができます。
住民税の支払い時期と方法

住民税は、前年の所得に基づいて課税され、毎年、1月1日時点(課税基準日)に市区町村に住所がある個人や、事務所・事業所・家屋敷を有する個人が負担します。支払いのスケジュールは原則として毎年同じで、6月に納税通知書が送付されるのが一般的です。実際の納期限は、6月、8月、10月、翌年1月の年4回に分割されます。このように、住民税は都度支払う「普通徴収」と、給与天引きによる「特別徴収」によって対応が異なる場合があります。
普通徴収と特別徴収の違い
住民税には、「普通徴収」と「特別徴収」の二つの仕組みがあります。普通徴収は個人が自分で納付書を用いて支払う方式で、自営業者や給与天引きに対応することができない方になります。一方、特別徴収は会社が従業員の給与から住民税を天引きし、代わりに納税する方法です。特別徴収は給与所得者にとって一般的な方式であり、会社へ自治体から直接通知が届き手続きを行います。このような仕組みの違いを理解し、自分に合った支払方法を確認してください。
会社員と自営業者で異なる支払方法
住民税の支払い方法は、会社員と自営業者の間で異なります。会社員の場合、特別徴収が一般的で、給与から天引きされるため、自分で納付手続きを行う必要がありません。一方、自営業者やフリーランスの場合は普通徴収となるため、自治体から送付される納付書に基づいて定められた期日までに支払う必要があります。収入形態の違いに応じた手続きを確認しておくとスムーズです。
未納や滞納時のペナルティ
住民税を期日までに支払わない場合には、延滞金などのペナルティが発生します。延滞金の利率は法律で定められており、未納期間が長くなるほど負担が大きくなります。また、一定期間納付がされない場合には財産差し押さえなどの強制的な徴収措置をとられることがあります。特に住民税は地域社会の公共サービスを維持するために重要な役割を果たす税金ですので、支払い遅れを防ぐためにも納期限をしっかり管理することが大切です。
住民税を効率よく抑える方法
ふるさと納税で住民税を節約
ふるさと納税は、住民税を効率よく節約する最も代表的な方法です。ふるさと納税とは、全国の自治体に寄付を行うことで、その額の一部が住民税や所得税から控除される制度です。自己負担は2,000円のみで、それ以上の寄付分については翌年の住民税が減額されます。たとえば、特定の地域に寄付をして地域特産品を受け取ることができる一方、その寄付金額が控除対象となる点が大きな魅力です。この仕組みにより、地方の活性化にも貢献しつつ、実質負担を減らすことができます。
住宅ローン控除と住民税の関係
住宅ローン控除とは、住宅を購入した際にローンを利用した場合に受けることができる税金の軽減措置です。この控除は主に所得税から引かれますが、所得税額が控除額を下回る場合には、住民税からも一部控除を受けることができます(所得税の課税総所得金額等の5%、最高9.75万円が上限)。具体的には、所得税の控除後に残る余剰分が住民税所得割から控除される仕組みです。ただし、控除の上限額は地方自治体ごとに異なるため、事前の確認が重要です。この制度を活用することで、少ない負担で大きな節税を実現できます。
医療費控除やそのほかの控除を活用
医療費控除は、自身や家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に適用される控除制度です。この控除によって課税所得が減額されるため、住民税の負担を軽減することができます。ほかにも、配偶者控除や扶養控除、小規模企業共済掛金控除など、さまざまな控除制度があります。これらの控除を上手に活用することで、住民税を効率的に抑えることができます。申告時に控除を漏れなく適用するため、日頃から領収書や書類を整理しておくことが大切です。
住民税の早見表をご紹介
| 年収(額面) | 住民税 |
| 300万円 | 122,900円 |
| 400万円 | 179,800円 |
| 500万円 | 247,900円 |
| 600万円 | 330,800円 |
| 700万円 | 381,700円 |
| 800万円 | 465,600円 |
| 900万円 | 553,400円 |
| 1000万円 | 651,400円 |
※上記は概算です。その他の影響で変わることがあります
※賞与は考慮せず、年収の12分の1を月額給与(標準報酬額)として概算しています
住民税に関するよくある質問

最後に住民税に関するよくある質問をまとめました。ご参考までにご覧ください。
住民税の非課税基準はどのくらい?
住民税には、課税対象を判断する非課税基準が存在します。この基準は各自治体によって若干異なる場合がありますが、一般的には所得が一定額を下回る場合に非課税となります。現行制度(2026年時点)では、単身世帯であれば給与収入100万円以下(合計所得45万円以下)が非課税基準(均等割・所得割ともに非課税)となることが多いです。また、扶養家族がいる場合や障害者控除が適用される場合は、基準額が引き上げられるため注意が必要です。詳細な非課税基準については、居住地の市区町村役場に問い合わせるとよいでしょう。
年末調整や確定申告との関係性とは?
住民税は所得を基に課税されるため、年末調整や確定申告と深く関係しています。会社員の場合、年末調整によりその年の収入や所得控除が確定し、その結果が税務署を通じて自治体に連絡されます。一方、自営業者や会社員でも副業収入がある場合などは、確定申告が必要です。この申告内容が基に住民税が計算され、翌年度の課税につながります。正しく申告を行わないと、住民税の額が不正確になり、後に修正が必要となることもあるので注意しましょう。
異動や引っ越し時の住民税の納め方
転職や引っ越しをした場合でも、住民税の納付は1月1日時点に住民票があった自治体に対して行います。これは、住民税が前年の所得を基に課せられるためです。たとえば、1月1日時点でA市に住んでいて、その後にB市へ引っ越した場合でも、住民税はA市に支払うことになります。また、会社を退職した場合は、それまで特別徴収(給与天引き)だった住民税が普通徴収(自分で納付)に切り替わる場合があります。この場合、自治体から送付される納税通知書に従い、期限内に支払いを行う必要があります。
まとめ

所得税は、最低税率5%〜最高税率45%の超過累進税率で、所得に応じて税率が変わりますが、住民税は一律10%です。さらに基礎控除や配偶者控除などの所得控除の多くは所得税より住民税の方が低く設定されているため、所得税額より住民税額の方が大きいという人も多いと思います。今回紹介した早見表を参考にしながら、負担を軽減できる所得控除を活用し、住民税と上手に付き合ってください。
高翔では住まいだけでなく、「暮らしの安心を支えるパートナー」として、あなたの未来を見据えた資産形成を応援しています。芦屋・阪神間で、資産形成でお悩みがありましたらお気軽に高翔までお問い合わせください。