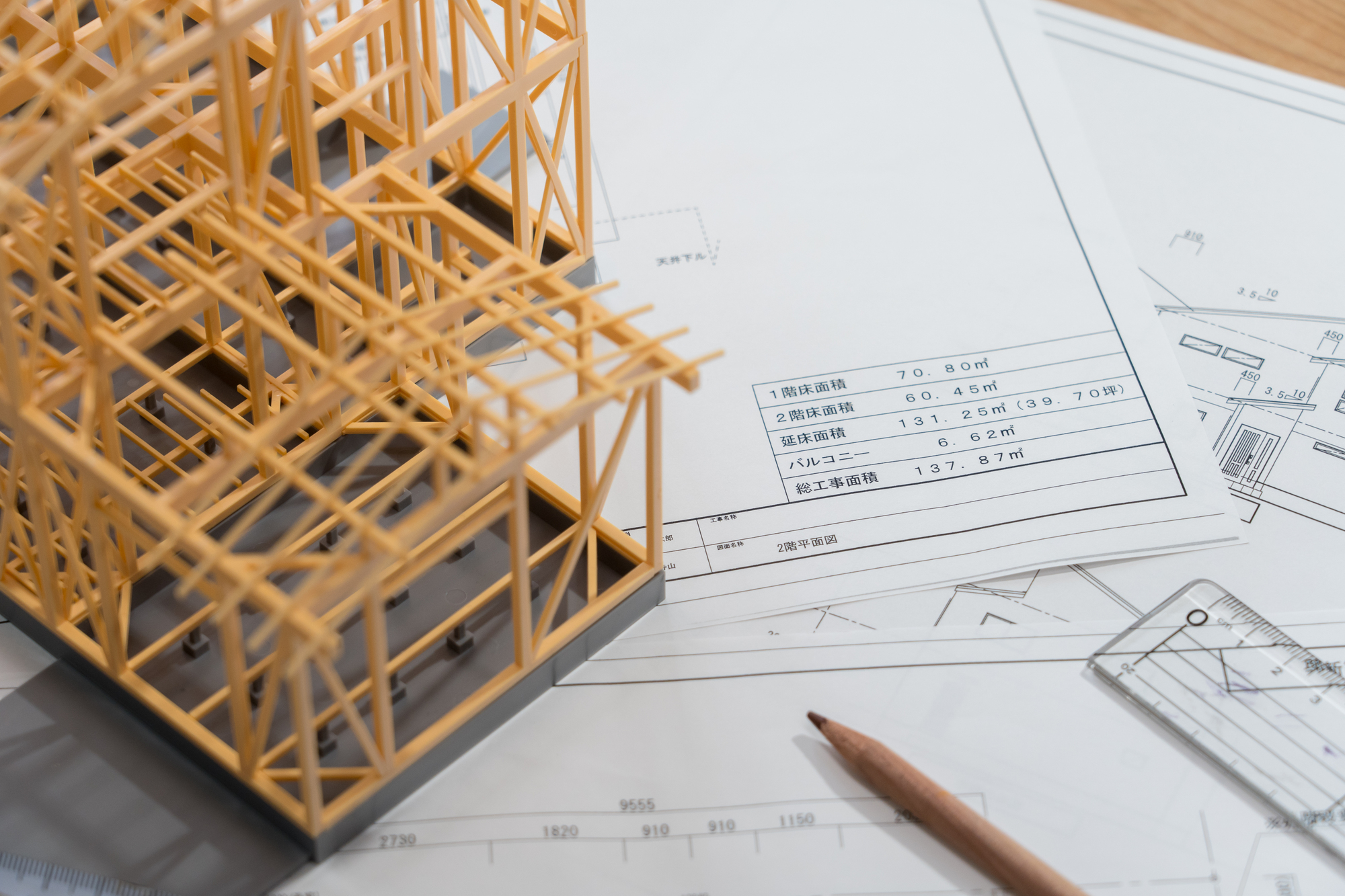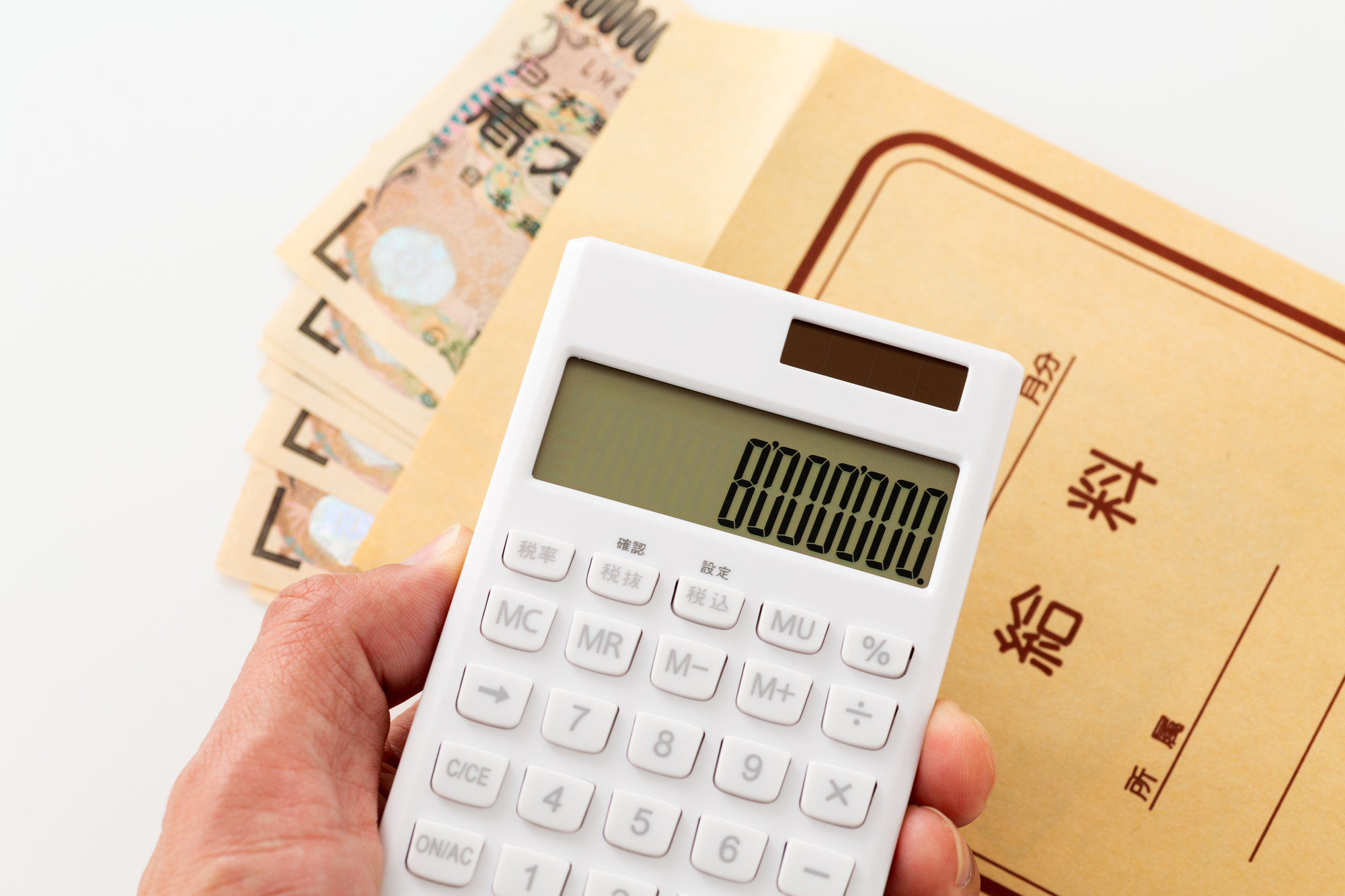住宅ローン控除は、マイホームを取得した際に所得税や住民税の一部が戻ってくる魅力的な制度です。ただし、手続きや条件を正しく理解していないとせっかくの控除を受け損ねることもあります。今回は、制度の概要から申請の流れ、控除額や注意点など2025年の最新情報をご紹介いたします。
兵庫県芦屋市 / 西宮市 / 神戸の家づくり
高翔のことを知って
“理想”の家づくりを始めてみませんか?
目次
住宅ローン控除とは

そもそも、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、マイホーム購入の負担を軽減するための税制優遇制度です。
住宅ローンの年末残高の0.7%が所得税などから控除され、「新築住宅は最長13年間、中古住宅は10年間」適用されます。
省エネ性能の高い住宅や、子育て世帯・若者夫婦は借入限度額や控除期間が拡大されるなどの優遇措置があります。
控除を受けるには、住宅の要件や本人の所得、居住開始時期などの条件を満たす必要があります。
【2025年】新しい住宅ローン控除の変更点
2025年の住宅ローン控除制度では、令和7年度税制改正によって一部の内容が変更されました。ただし、基本的には2025年度の税制改正大綱に記載されている内容は、2024年の変更点を引き継ぐものとなっています。
現行の住宅ローン減税と同様に、住宅ローンの年末残高に応じた控除(所得税の還付)が受けられる仕組みとなっていますが、控除対象となる物件や借り入れ限度額の要件が見直されています。
| 項目 | 2025年度の改正・変更点 |
| 子育て・若者世帯優遇 | 対象世帯の借り入れ限度額が引き上げられ、控除期間も最大13年と長く設定されています。引き続き優遇措置が受けられます。 |
| 省エネ住宅要件 | 新築住宅は原則、省エネ基準を満たさなければ控除対象外になります。一定条件下では経過措置があります。 |
| 床面積緩和 | 所得が1,000万円以下の人は、40㎡以上あれば控除可能になります。(通常は50㎡以上)2025年確認分までの特例となっています。 |
| 贈与税非課税枠 | 非課税措置が延長され、ZEH水準住宅なら非課税枠が最大1,500万円に拡大しています。 |
| リフォーム減税 | 減税制度が延長され、子育て・若者世帯向けのリフォームにも新たな控除制度が追加されました。 |
新築住宅の取得に係る住宅ローン減税(2022年~2025年入居)
2025年に新築住宅へ入居する場合、借り入れ限度額が以下のように設定されています。
▼2025年に新築住宅に入居した場合
| 住宅の種類 | 世帯区分 | 借り入れ限度額 | 年間控除上限額 | 最大控除額(13年) |
| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 一般世帯 | 4,500万円 | 31.5万円 | 409.5万円 |
| 子育て・若者世帯 | 5,000万円 | 35.0万円 | 455.0万円 | |
| ZEH水準省エネ住宅 | 一般世帯 | 3,500万円 | 24.5万円 | 318.5万円 |
| 子育て・若者世帯 | 4,500万円 | 31.5万円 | 409.5万円 | |
| 省エネ基準適合住宅 | 一般世帯 | 3,000万円 | 21.0万円 | 273.0万円 |
| 子育て・若者世帯 | 4,000万円 | 28.0万円 | 364.0万円 |
中古住宅の取得に係る住宅ローン減税(2022年~2025年入居)
中古住宅の場合も、2025年までの入居を条件として住宅ローン控除の適用が可能です。
▼2025年に中古住宅(既存住宅)に入居した場合
| 住宅のタイプ | 借り入れ限度額 | 年間控除上限額 | 最大控除額(10年) |
| 長期優良住宅・低炭素住宅 | 3,000万円 | 21万円 | 210万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | |||
| 省エネ基準適合住宅 | |||
| その他の住宅 | 2,000万円 | 14万円 | 140万円 |
適用条件
住宅ローン控除を受けるためには、以下の条件を満たしている必要があります。
1.住宅購入後6ヵ月以内に居住し、控除を受ける年の年末時点まで住み続けていること
2.合計所得金額が2,000万円以下であること
3.住宅ローンの返済期間が10年以上であること
4.住宅の床面積が原則50㎡以上であること
※40~50㎡は所得1,000万円以下の人のみ対象
5.2024年以降に建築確認を受ける新築住宅は、省エネ基準適合住宅であること(認定住宅、ZEH水準等)
6.親族や同族会社など、特別関係者からの取得ではないこと
7.自己名義で登記されていること(共有の場合は持分割合に応じて適用)
8.新築・中古・買取再販住宅・リフォームなど(各種性能・耐震要件を満たすこと)
適用期間
2025年の住宅ローン控除は、基本的に2022年から2025年の間に入居した物件が対象となります。
適用される期間は、住宅の種類によって変わります。
・新築を購入した場合は基本的に13年間
・中古住宅の取得やリフォームの場合は10年間
控除額は各年の年末時点におけるローン残高の0.7%で算出されるため、元金の返済が進むにつれてローン残高が減少し、それに伴って控除額も年々少なくなっていく仕組みです。そのため、制度上の適用期間が13年または10年と設定されていても、実際に受けられる控除の金額は年を追うごとに縮小していきます。
住宅ローン控除の対象とならない場合とは?

2025年の住宅ローン控除制度において、以下の条件に該当する場合は控除の対象外となります。これらの要件を正確に把握し、計画を進めることが重要です。
| 対象外となるケース | 解説 |
| 省エネ基準未適合の新築住宅 | 2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅で、省エネ基準を満たしていない場合は対象外 |
| 「その他の住宅」で要件未証明 | 中古住宅のうち、「その他の住宅」に該当する場合、登記簿上で建築確認日や省エネ基準への適合を証明できないと対象外です。 |
| 中古住宅の耐震未適合 | 中古住宅のうち、「その他の住宅」に該当する場合、登記簿上で建築確認日や省エネ基準への適合を証明できないと対象外です。、耐震改修工事を行い、その証明がないと対象外 |
| 親族からの贈与取得 | 親族から贈与された住宅を取得した場合は、自己資金での購入となり、住宅ローン控除の対象外です。 |
| 床面積50㎡未満 | 住宅の床面積が50㎡未満の場合は控除対象外。ただし、合計所得金額が1,000万円以下の人であれば、床面積が40㎡以上50㎡未満でも住宅ローン控除の対象になります。 |
| 合計所得金額2,000万円超 | 合計所得金額が2,000万円以下の人が対象であり、超えると控除対象外です。 |
| 返済期間が10年未満 | 住宅ローンの返済期間が10年未満のローンは控除対象外です。 |
| 入居が取得日から6ヶ月を過ぎた場合 | 住宅の取得後、遅くとも6か月以内に実際に居住を開始していない場合は控除対象外です。 |
2025年住宅ローン控除を受けるときの注意点【手続き・制度面】

控除を受けるためには確定申告や年末調整など、いくつかの重要な手続きや制度上の条件があります。
手続きの不備や制度の誤解によって本来受けられるはずの控除が無効になってしまうケースもあるため、事前に正しく理解しておくことが大切です。
それでは、住宅ローン控除を受けるときの注意点をご紹介いたします。
1.確定申告・年末調整が必要
住宅ローン控除を受けるには、正しい手続きを行う必要があります。
特に初年度は確定申告が必須となり、その後は年末調整によって控除が適用され続けます。詳しくは、後ほど解説いたします。(見出し:住宅ローン控除を受けるための手続き)
2.居住開始の「年」に控除スタート
住宅ローン控除は、住宅に実際に住み始めた年(居住開始年)から適用されます。
例えば住宅の引渡しが早くても、実際の居住が遅れるとその年は控除の対象外となるため注意が必要です。
原則として、住宅の取得日から6か月以内に入居しなければ、控除の適用を受けることができません。
3.上限額まで還付されるとは限らない点に注意
住宅ローン控除では、最大控除額がそのまま全額戻るわけではありません。
控除額は、ローン残高や返済の進行状況によって変わります。
たとえば、ZEH水準の省エネ住宅で4,500万円を借り入れた場合、初年度の控除は31万5,000円となりますが、返済により残高が減ると控除額も徐々に少なくなり、残高が4,000万円なら約28万円、2,000万円まで減れば約14万円に縮小します。
また、もともとの借り入れ額が少ないケースでは、最大控除額に届かないこともあります。
住宅ローン控除を受けるための手続き

住宅ローン控除を受けるには、確定申告または年末調整の手続きを正しく行う必要があります。初年度は確定申告が求められ、それ以降の年は勤務先に必要書類を提出することで年末調整で控除が適用されます。手続きに際しては、物件の購入契約書や住宅ローンの契約書などの必要書類を事前に準備することが非常に重要です。
それでは、「初年度」と「2年目以降」の2つに分けてご紹介いたします。
【初年度】は「確定申告」が必要
初めて住宅ローン控除を受ける年は、会社員であっても自分で確定申告を行う必要があります。
提出期限は、翌年の確定申告期間(通常は2月中旬~3月中旬)までに提出する必要があります。
◯提出書類の例
・住宅借入金等特別控除の明細書
・住民票の写し
・登記事項証明書
・売買契約書または請負契約書の写し
・ローンの年末残高証明書
【2年目以降】は「年末調整」(会社員の場合)
初年度に確定申告を済ませていれば、2年目以降は勤務先の年末調整で控除を受けられます。(自営業などは引き続き確定申告が必要)
毎年の年末調整時に、勤務先へ提出しましょう。
◯必要書類
・税務署から送付される「住宅借入金等特別控除申告書」
・金融機関が発行する「年末残高証明書」
このように、初年度は確定申告による申請が必須で、2年目以降は簡略化されるため、初年度の手続きを正確に行いましょう。
住宅ローン控除の確定申告書の書き方(初年度)
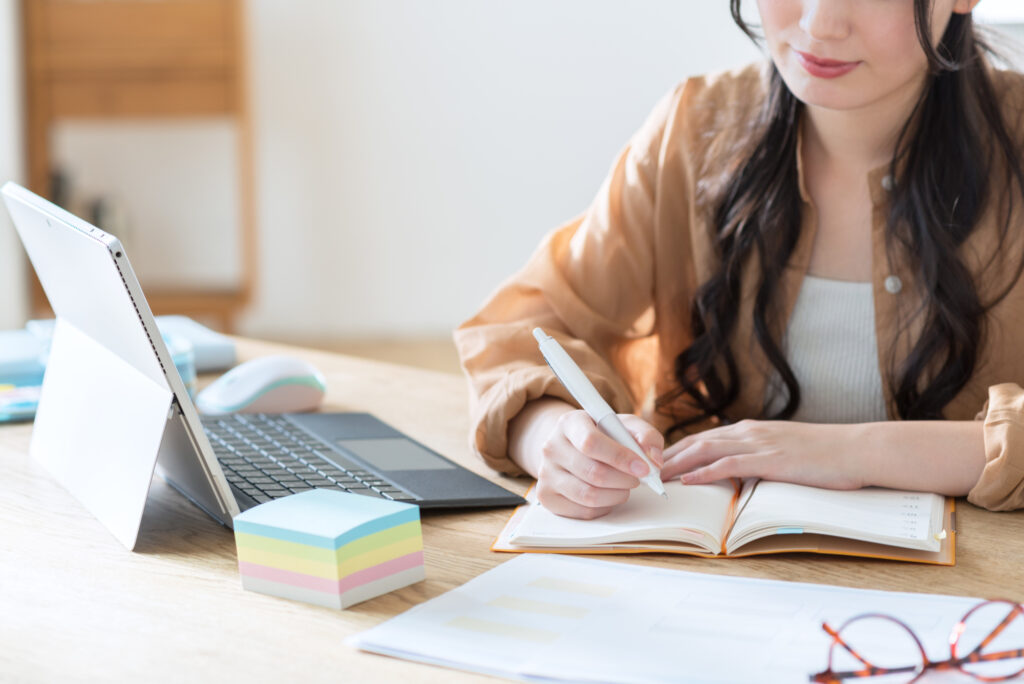
住宅ローン控除を受けるには、マイホームを購入した初年度に「確定申告」の手続きが必要です。会社員の方でも申告が必須となり、手続きを行わないと控除を受けられません。初年度に行う確定申告に必要な書類や手続きの流れをわかりやすくご紹介いたします。
【ステップ①】必要書類を準備
申告書を記入する前に、以下の書類をそろえましょう
| 書類名 | どこで手に入るか |
| 住宅ローンの年末残高証明書 | ローンを組んだ金融機関から届く(10月~11月頃) |
| 売買契約書・請負契約書の写し | 契約時に作成したもの |
| 土地・建物の登記事項証明書 | 法務局またはオンライン取得 |
| 住民票の写し | 市区町村役所またはコンビニ交付可 |
| 本人確認書類(マイナンバー含む) | マイナンバーカード or 通知カード+免許証など |
| 認定住宅等の証明書の写し(該当者) | ハウスメーカー等から交付 |
【ステップ②】申告書を入手
以下いずれかの方法で申告書を準備します。
・紙の申告書(A様式):税務署で入手 or 国税庁HPからダウンロード
・e-Tax:国税庁「確定申告書等作成コーナー」からオンライン作成(おすすめ)
※自営業、フリーランスなどの事業所得者、不動産所得、雑所得などがある人は「申告書B様式」を使用します。
【ステップ③】確定申告書の主な記入項目
確定申告書には、住宅ローン控除を受けるために必要な情報を正確に記入します。
主に記入する項目としては、購入した住宅の所在地や建築面積、借り入れ金額とその年末残高などがあります。
▼確定申告書A 第一表
| 項目 | 内容 |
| ① 氏名・住所・生年月日など | 申告者本人の基本情報を記入 |
| ② 所得の種類(給与など) | 会社員の場合は「給与」欄に源泉徴収票の情報を転記 |
| ③ 所得控除 | 各種控除(医療費控除・社会保険料控除など)を記入。
※住宅借入金等特別控除はここには記入しない(別の用紙で入力) |
| ④ 税額・還付金額など | 所得税額、還付される税額などの自動計算結果が表示される欄 |
▼確定申告書A 第二表
| 項目 | 内容 |
| ① 所得の内訳 | 勤務先名・所在地・支払金額・源泉徴収税額などを記入 |
| ② 所得控除の内訳 | 社会保険料控除、生命保険料控除、小規模企業共済などの詳細 |
| ③ 住民税・事業税に関する事項 | 住民税で控除を受けたい控除内容を選択 |
| ④ 配偶者・扶養親族の情報 | 氏名・マイナンバー・生年月日・所得金額など |
| ⑤ その他 | 雑損控除や寄附金控除、外国税額控除などの詳細欄 |
▼【別紙】住宅借入金等特別控除額の計算明細書
| 項目 | 内容 |
| ① 居住開始年月日 | 実際に住宅へ住み始めた日 |
| ② 家屋の取得年月日・床面積 | 住宅を購入・建物が完成した日付と家屋の登記事項証明書に記載の床面積 |
| ③ 住宅ローンの借入先・借入日・借入金額 | 金融機関名、借入日、ローン契約金額などを記入 |
| ④ 年末残高 | その年の住宅ローンの年末時点の残高(証明書に記載) |
| ⑤ 控除対象となる家屋の用途 | 自己の居住用かどうかを確認 |
| ⑥ 控除額の計算欄 | ローン残高 × 控除率(通常0.7%)で算出 |
ご不明な点がある場合は、税務署や確定申告会場、税理士などに相談してみましょう。
e-Taxであれば、画面の指示に従って入力すれば、自動で書類が完成するため、おすすめです。
【ステップ④】書類を添付・提出
◯添付書類台紙に貼り付けるもの
・年末残高証明書
・登記事項証明書
・売買契約書または請負契約書のコピー
・源泉徴収票(原本)
※源泉徴収票は、提出書類ではあるが「台紙」には貼らず、申告書と一緒に同封または添付欄に挿入します。
◯提出方法
・税務署に直接持参または郵送
・e-Tax(電子申告)でオンライン提出
初年度の手続きは複雑に感じるかもしれませんが、一度行えば翌年以降は手間が大幅に減ります。
住宅ローン控除に関するよくある質問
住宅ローン控除は2025年になくなりますか?
いいえ、住宅ローン控除は、2025年になくなるわけではありません。
現行の制度が2025年末の入居までを適用期限としています。2026年以降については、今後の税制改正で新たな制度が設けられるか、現行制度が延長される可能性がありますが、現時点では未定です。
住宅ローン控除の確定申告は2025年のいつからですか?
2025年中に住宅に入居した場合、住宅ローン控除の確定申告は、その翌年である2026年の2月中旬から3月中旬に行います。
住宅ローン控除とふるさと納税は併用できますか?
はい、併用できます。ただし、注意が必要です。
ワンストップ特例制度を利用せず、確定申告でふるさと納税の控除を申請する場合、所得税からまず住宅ローン控除が優先的に引かれます。
その結果、所得税額がゼロまたは少なくなると、ふるさと納税による所得税の還付額が減ることがあります。
ただし、所得税で引ききれなかった控除額は住民税から控除されるため、控除上限額内であれば自己負担2,000円を除いた全額が控除される仕組みに変わりはありません。
兵庫県で家づくりを検討しているなら高翔にご相談ください

兵庫県で注文住宅をご検討されている方は、地元密着型のサポートを提供する「高翔」にご相談ください。
当社では、最新の制度情報や省エネ住宅の建築要件に基づいた適切なプラン提案を行っています。
さらに、2025年における制度改正を踏まえ、所得に応じた住宅ローンの借り入れ限度額や控除額についてもプロの目線でアドバイスし、納得のいく家づくりをお手伝いいたします。
初めて住宅取得を検討される方や、ローンや所得税に詳しくない方でも安心していただける体制を整えております。ぜひ、お気軽にご相談ください。