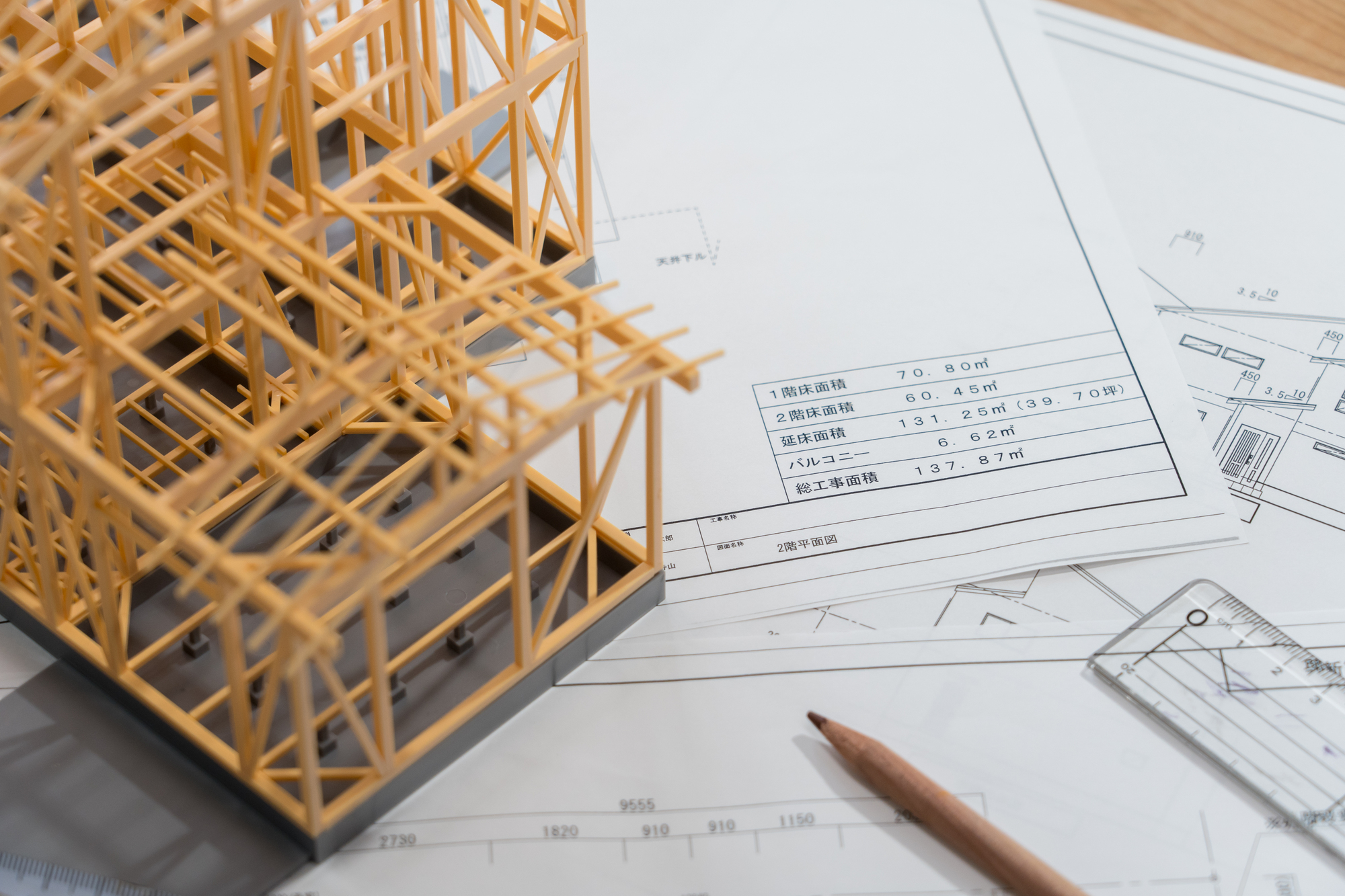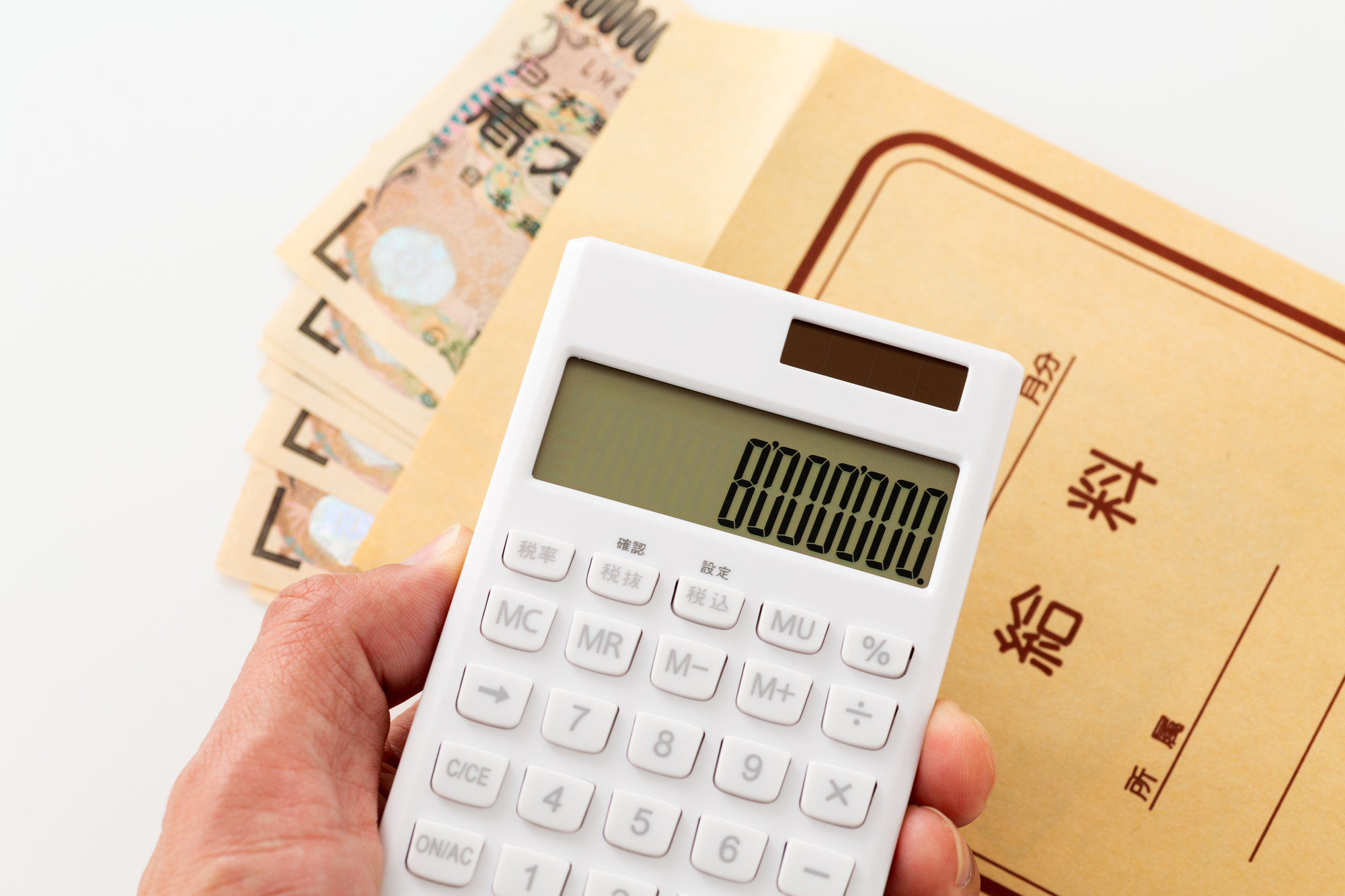「夏は暑く、冬は寒い…」そんな住宅の快適性は「断熱等級」で大きく変わります。
光熱費にも直結するこの等級は、後悔しない住宅づくりの重要な重要な基準です。
この記事では、断熱等級の基本から性能の違いまでをわかりやすく解説いたします。
兵庫県芦屋市 / 西宮市 / 神戸の家づくり
高翔のことを知って
“理想”の家づくりを始めてみませんか?
目次

断熱等級とは
断熱等級とは、住宅の断熱性能を数値化した指標であり、住まいの快適性や省エネルギー性を判断するための重要な基準です。
「UA値(外皮平均熱貫流率)」と呼ばれる数値をもとに算出され、値が小さいほど断熱性能が優れていることを示します。
具体的には、室内と外気の熱のやりとりが少なくなるほど、高い断熱等級に分類されます。
現在の日本では、断熱等性能等級として1から7までの等級が設定されていますが、特に近年、等級4以降が注目されています。等級4は国の省エネ基準を満たすレベルで、等級5から等級7は、それ以上に高い断熱性能を持つ住宅を指します。
各断熱等級(3~7)の違い

断熱等級は各等級それぞれで基準が異なり、等級が上がるほど(等級の数字が高いほど)住宅の断熱性能が優れていることを示します。
それでは、各等級の特徴をわかりやすく解説いたします。
断熱等級4
断熱等級4は1999年に導入された次世代省エネルギー基準に基づく等級で、現在の基準では最低限必要な断熱性能を指します。
この等級では、従来の住宅と比較して冷暖房効率が向上し、省エネルギー性がある程度改善されます。しかし、特に寒冷地では快適性やエネルギー消費において物足りない場合があるため、今後の住宅建築では等級5以上が推奨される傾向にあります。
断熱等級5
断熱等級5は2022年4月に新設された基準で、UA値0.6以下が求められる、ZEH(ゼッチ)水準の等級です。
この等級では、エアコンなどの冷暖房効率がさらに向上し、全体的な光熱費の節約につながることが特徴です。
等級4と比べて外気温の影響を受けにくくなり、年間を通して安定した室内環境が実現しやすくなります。
断熱等級6
断熱等級6は2022年10月に新設された基準で、UA値0.46以下が求められ、高断熱の住宅をつくるための新しい指標となっています。
この等級を満たす住宅は、エネルギー消費量がさらにおさえられ、冷暖房による光熱費の節約効果が一層高まります。
また、室温が安定しやすく、ヒートショックや熱中症リスクを軽減できる環境が整えられます。
断熱等級7
断熱等級7は現在の最高基準で、UA値0.26以下が求められます。
この等級は断熱性能が非常に高く、外気温の影響をほぼ受けない「超高断熱住宅」になります。
たとえば、寒冷地でも暖房に頼らず快適な環境を維持することが可能になることもあります。
また、冷暖房エネルギーが大幅に削減されるため、カーボンニュートラル推進においても非常に有効な住宅性能といえます。
断熱等級と一次エネルギー等級を意識した設計によって、持続可能な住宅環境を実現するためには、この等級7が理想的な目標になるといえるでしょう。
2025年の省エネ基準適合義務化について
2025年4月から、日本の住宅建築は大きな転換点を迎えます。
改正建築物省エネ法の施行により、原則としてすべての新築住宅・非住宅に対して「省エネ基準」への適合が義務付けられることになりました。
これまで努力義務に留まっていた小規模な住宅にも適用されるため、これから住宅をつくるすべての人に関わる重要な法改正です。
この法改正は、2050年のカーボンニュートラル(温室効果ガス排出実質ゼロ)実現に向けた取り組みの一環です。
家庭部門のエネルギー消費をおさえるため、新しく建てられる住宅の省エネ性能を一定以上に引き上げることを目的としています。
断熱等級を高くするメリット
光熱費を大幅に節約できる
断熱等級を高めることで、住宅の保温性が向上し、冷暖房効率が大幅にアップします。
これにより、エアコンの冷房や暖房の使用頻度が減少し、光熱費を大幅に節約することが可能です。
たとえば、国土交通省の資料によると、兵庫県(省エネ地域区分6)で断熱等級4の住宅と、ZEH水準である等級5の住宅を比較した場合、年間で約2.6万円の光熱費の差が出ると試算されています。
さらに高性能な等級6の住宅であれば、その差は年間4万円以上にもなります。
一年中過ごしやすい室内環境
断熱等級の高い住宅は、まるで魔法瓶のように外気の影響を受けにくく、室内の快適な温度を長く保ちます。
冬は暖房の熱が逃げず、リビングと廊下・脱衣所との温度差も少ないためヒヤッとしません。夏は外の熱気を遮り、一度冷房で涼しくなればその効果が長続きします。
住宅のなかの不快な温度差をなくし、一年を通してストレスの少ない健康的な暮らしを実現します。
ヒートショックやアレルギーのリスクを軽減
高断熱住宅は、室温の急激な変化を防ぎやすいため、ヒートショックのリスクをおさえることができます。
ヒートショックは、浴室やトイレなどの寒暖差が激しい場所で起こりやすい現象で、高齢者は特に注意が必要です。
また、外気が入りにくい構造にすることで、花粉の侵入を防ぎやすくなり、アレルギーのリスクも抑制されます。
住宅の資産価値向上とほかのメリット
断熱等級を高めた住宅は、高い品質と省エネ性能が評価されるため、資産価値が向上する場合があります。
特に、長期優良住宅に認定されると、住宅ローン控除や補助金を受けやすくなる点もメリットです。
また、環境への配慮が進む現代社会において、カーボンニュートラル実現に貢献する住宅として、より多くの注目を集めることが予想されます。
断熱等級を高くするデメリット・注意点
建築コストが高くなる
断熱等級を高くするためには、性能のよい断熱材や窓ガラス、高気密な施工が必要となります。
これらの高性能な建材を導入したり、施工の技術を確保したりするためには、初期の建築コストがどうしても高くなってしまうのが現実です。
特に、断熱等級6や7を目指す場合、標準仕様の住宅と比べてコストが増加する可能性があります。
夏場に室内が暑くなりすぎる「夏型結露(オーバーヒート)」が起こる場合も
断熱性能を上げることで、冬場の寒さを効果的に防ぐことができますが、その一方で夏場にクーラーを止めると室内の熱が溜まりやすくなりこもりやすくなり、「夏型結露(オーバーヒート)」と呼ばれる現象が起こる可能性があります。
特に、日射が強い地域では、窓ガラスから太陽光が室内に入り込んで熱を蓄積することが問題となります。
このような場合、断熱性だけでなく、遮熱性能の高い窓や適切な換気計画、庇や日除けといった設計要素が必要です。
断熱等級が高い住宅をつくる際のコツ
「UA値」だけでなく「C値」も重視する
断熱等級を高くする際、よく耳にするのが「UA値」です。
UA値は住宅の断熱性能を数値化したもので、これが低いほど熱が外に逃げにくい住宅となります。
しかし、UA値だけで住宅の性能を判断するのは十分ではありません。同時に重視すべきなのが「C値」です。
C値とは住宅の気密性を数値化したもので、値が小さいほど隙間が少なく、冷暖房効率が向上します。
たとえば、いくら断熱材を厚くしてUA値を下げたとしても、隙間が多いと熱が逃げてしまい、夏は暑く冬は寒い環境になりがちです。
そのため、断熱性も気密性もバランスよく設計することが、快適で省エネな住宅を実現するうえで重要なポイントです。
窓の性能と配置にこだわる
窓は住宅のなかで最も熱が出入りしやすい部分です。
そのため、窓の性能にこだわることは断熱性能を高めるうえで非常に重要です。
具体的には、「トリプルガラス」や「樹脂製サッシ」を採用することで、高い断熱効果が期待できます。
また、窓の配置も重要です。
たとえば、日射をたくさん取り込みたいリビングでは南向きに窓を設けることが一般的ですが、西からの直射日光を防ぐために西側の窓の大きさや位置を調整することも重要です。
断熱等級を向上させるためには、こうした窓の性能や配置の計画が必要です。
実績のある住宅会社に依頼する
断熱等級の高い住宅をつくるには、信頼できる住宅会社に依頼することが成功の鍵です。
経験豊富な住宅会社は、断熱等級に関する疑問にも的確に答えてくれます。
また、「住宅性能表示制度」などにも精通しているため、基準を満たした高性能住宅の建築が可能になります。
さらに、最新の断熱技術や省エネ基準に対応するための補助金制度などについても提案してくれる会社を選ぶと、初期コストをおさえながら理想の住宅を実現できます。
高性能な注文住宅をつくるなら高翔

高翔の注文住宅は、断熱性能を示すUA値だけでなく、気密性を表すC値にもこだわり、高い基準をクリアした住宅をご提供しています。
また、断熱性を高めるだけでなく、窓の性能や配置にも工夫を凝らし、エネルギー効率の高い設計を実現しています。
省エネ性能や環境への配慮を重視した住宅をお考えの方は、ぜひ高翔にご相談ください。
快適で経済的な暮らしを実現するための最適なご提案をいたします。