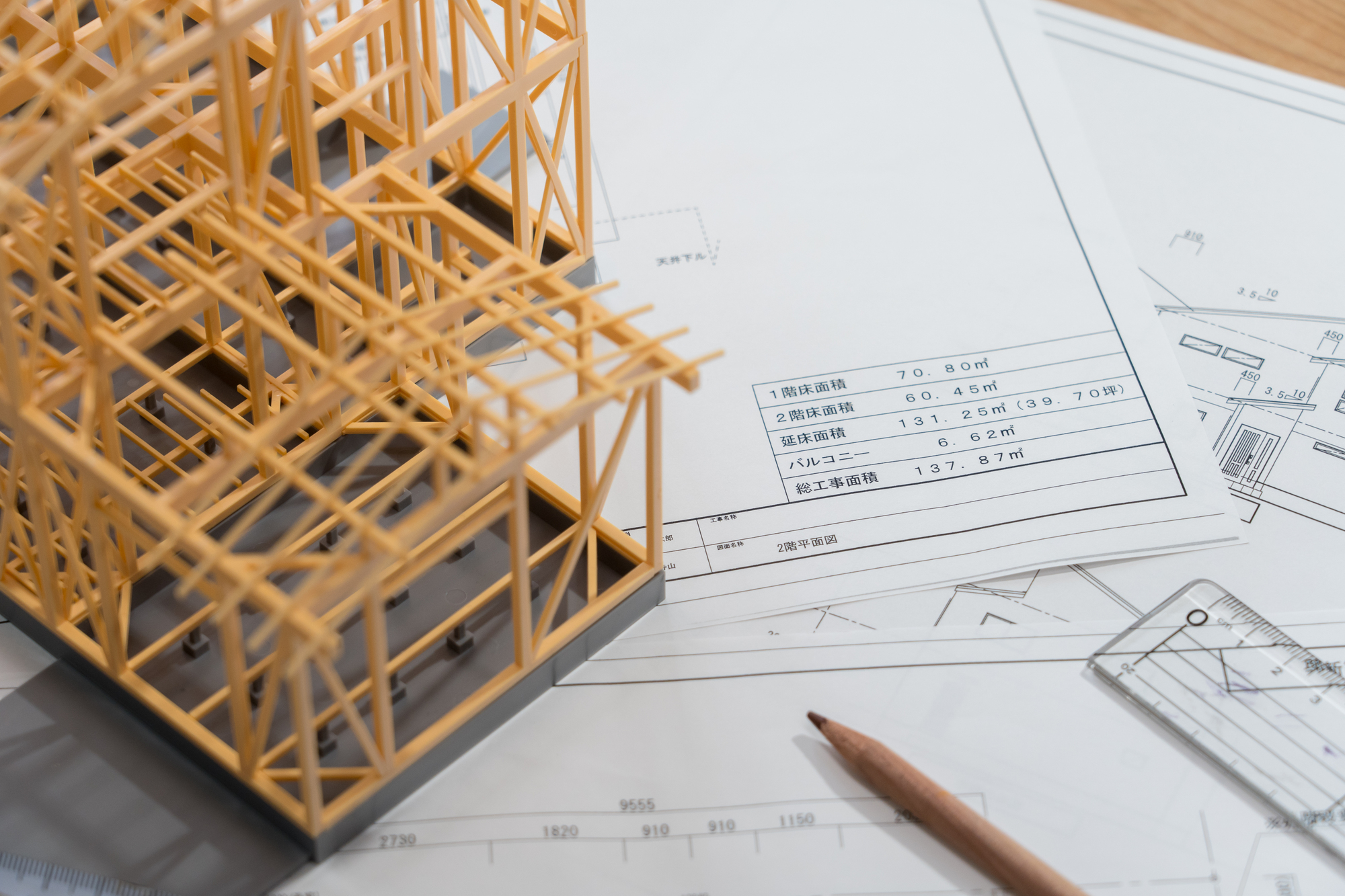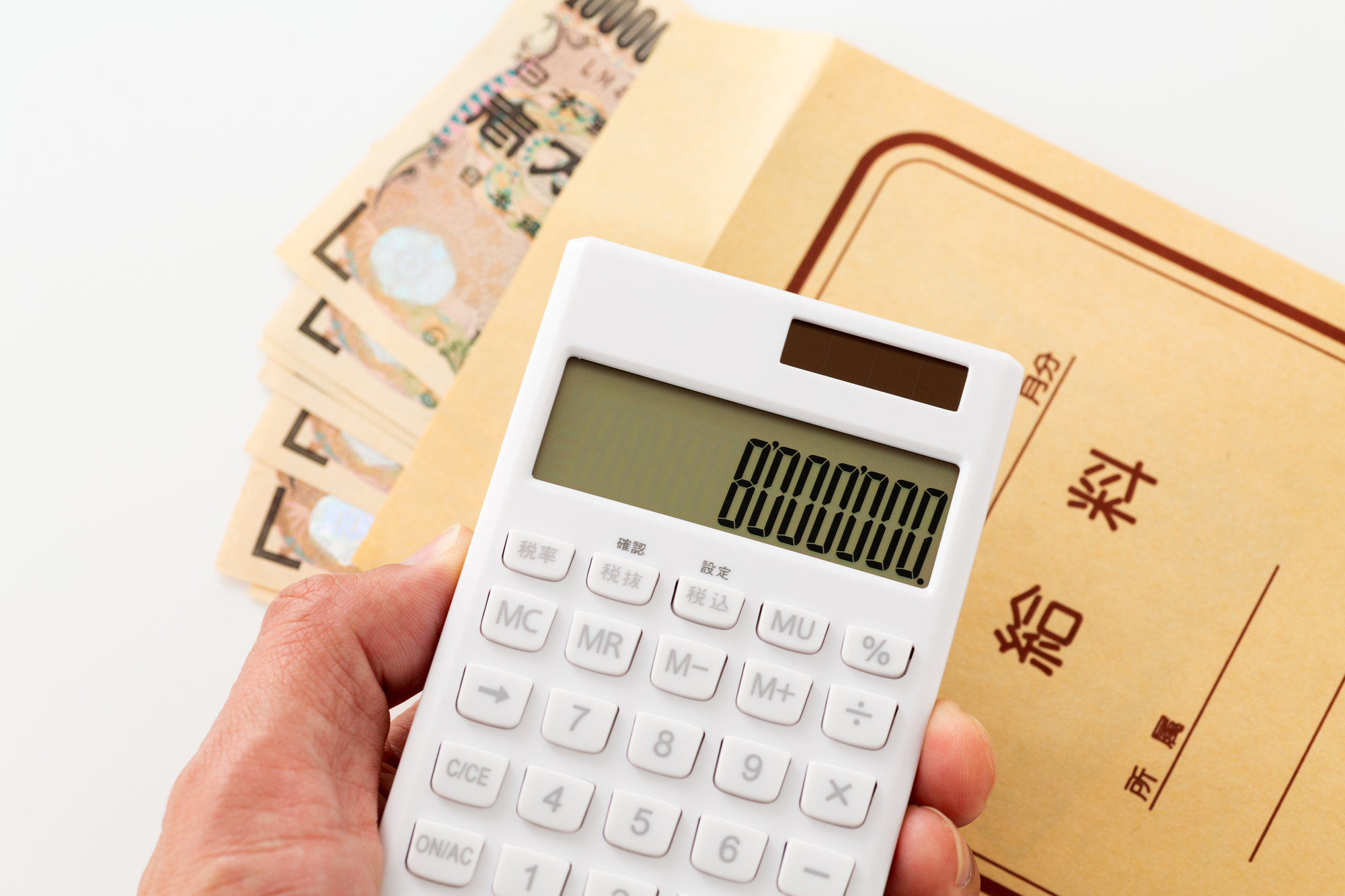家を建てるなら知っておきたい「長期優良住宅」。言葉は聞くけれど、詳しくはわからない方も多いのではないでしょうか?
この記事では、制度の基本からメリット、申請の流れまで、基本的な情報をわかりやすくご紹介いたします。
兵庫県芦屋市 / 西宮市 / 神戸の家づくり
高翔のことを知って
“理想”の家づくりを始めてみませんか?
目次
長期優良住宅とは?基本をわかりやすく解説

長期優良住宅とは、国が定める厳しい基準をクリアした、世代を超えて長く快適に住み続けられる高性能な住宅のことです。認定を受けると税金の優遇など多くのメリットがありますが、「なんとなく良さそう」というイメージだけでは分かりにくい部分も多いでしょう。ここでは、制度の目的から一般的な住宅との違い、そして認定に必要な性能基準まで、長期優良住宅の基本をわかりやすく解説いたします。
長期優良住宅制度の目的と概要
長期優良住宅制度は、丈夫で長持ちし、維持管理もしやすい質の高い住宅を普及させるための国の認定制度です。「作っては壊す」社会から、良い住宅を長く大切に使う社会へ転換し、住宅の資産価値向上や環境負荷の低減を図ることを目的としています。
▼認定実績【新築】
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 累計※1 | ||
| 認定実績
(新設住宅着工戸数に対する割合) |
一戸建ての住宅 | 115,509戸
(29.3%) |
111,341戸
(31.3%) |
136,842戸
(39.3%) |
1,694,243戸 |
| 共同住宅等 | 2,526戸
(0.5%) |
4,821戸
(1.1%) |
8,231戸
(1.8%) |
41,565戸 | |
| 総戸数 | 118,035戸
(13.7%) |
116,162戸
(14.5%) |
145,073戸
(17.8%) |
1,735,808戸 | |
※1 累計:平成21年6月~令和7年3月
※出典:国土交通省ウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_001283.html)
一般的な住宅との4つの大きな違い
一般的な住宅との主な違いは4点です。
①耐震性や省エネ性など法律で定められた高い性能を持つこと。
②建築後に定期的な点検・修繕の義務があること。
③税金の優遇措置や住宅ローンの金利引き下げといったメリットがあること。
④資産価値が維持されやすいこと。
認定を受けるために必要な性能基準とは?
認定には複数の基準を満たす必要があります。
具体的には、以下になります。
・劣化性
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
・耐震性
極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。
・省エネルギー性
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
・維持管理・更新の容易性
構造躯体に比べて耐用年数が短い設備配管について、維持管理(点検・清掃・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
・居住環境
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
・住戸面積
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
・維持保全計画
建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。
・災害配慮
自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。
上記のような多岐にわたる項目が定められています。
長期優良住宅の7つのメリット

長期優良住宅を選ぶ最大の魅力は、その多彩なメリットにあります。税金や補助金といった金銭的な恩恵だけでなく、日々の暮らしの快適さや将来の安心も手に入ります。ここでは具体的な7つのメリットをわかりやすく解説いたします。
税金の優遇措置が受けられる(住宅ローン控除・固定資産税など)
住宅ローン控除の借入限度額が一般住宅より大きくなり、所得税の還付額が増えます。また、不動産取得税や登録免許税も軽減されます。さらに、新築戸建ての固定資産税が減額される期間が、通常3年間のところ5年間に延長されるなど、様々な税制優遇が受けられます。
補助金制度が活用できる
長期優良住宅を対象とした国の補助金制度を利用できる場合があります。これらの補助金は、質の高い木造住宅の建築費用の一部を支援するものです。補助金を活用することで、初期費用を抑えながら高性能な住宅を建てることが可能になります。
地震保険料が割引になる
長期優良住宅は、認定基準で高い耐震性が求められます。このため、地震保険料が割引される「耐震等級割引」が適用され、耐震等級に応じて保険料が最大で50%割引されます。
住宅ローンの金利が優遇される(フラット35など)
住宅金融支援機構が提供する長期固定金利の住宅ローン「フラット35」において、金利が一定期間引き下げられる「フラット35S(金利Aプラン)」を利用できます。これにより、一般の住宅ローンよりも低い金利で借り入れができ、毎月の返済額や総返済額を抑えることが可能です。
家の資産価値が維持されやすい
国が定めた基準をクリアした高性能な住宅であるため、中古住宅市場においても高く評価される傾向があります。また、建築時やメンテナンスの履歴が「いえかるて」として保管されるため、売却時に買い手へ安心感を与え、適正な価格での取引が期待でき、資産価値が落ちにくいです。
耐震性・省エネ性が高く快適で安全な暮らしが実現する
高い耐震基準(耐震等級2以上など)を満たしているため、大地震への備えとなり安全な暮らしを守ります。また、優れた断熱性・省エネ性により、夏は涼しく冬は暖かい快適な室内環境を保ちやすく、年間の光熱費を削減できるというメリットもあります。
将来のメンテナンスコストを計画的に抑えられる
認定を受けるには、建築後の維持保全計画の策定が義務付けられています。この計画に沿って定期的な点検や修繕を行うため、建物の劣化を早期に発見・対応できます。突発的な大規模修繕を防ぎ、長期的に見たトータルのメンテナンスコストを計画的に管理しやすくなります。
長期優良住宅のデメリットと注意点

メリットの多い長期優良住宅ですが、後悔しないためにはデメリットの理解が不可欠です。建築コストや申請の手間、将来の義務など、計画前に必ず知っておきたいポイントをわかりやすく解説いたします。
建築コストが割高になる
高い耐震性や省エネ性を確保するため、高性能な建材や断熱材の使用、詳細な構造計算が必要になります。これにより、一般的な住宅と比較して建築コストが数十万円から数百万円程度高くなる傾向があります。初期費用が増加することは、計画段階で理解しておくべき重要な点です。
申請に手間と費用がかかる
認定を受けるには、設計段階で基準を満たしていることを証明する多くの書類を作成し、所管行政庁へ申請する必要があります。手続きが複雑なため専門家に依頼することが多く、申請手数料や書類作成の代行費用として数十万円程度の追加費用が発生することもデメリットと言えます。
建築後の定期的なメンテナンスと報告義務がある
建築時に作成した「維持保全計画」に基づき、定期的な点検や修繕を計画的に実施する義務を負います。また、自治体から求められた際にはメンテナンスの状況を報告する必要があり、これを怠ると認定が取り消される可能性もあるため、継続的な管理意識が求められます。
間取りやデザインに一部制約が出ることがある
高い耐震性を確保するために必要な壁や柱の量・配置が定められていたり、将来のメンテナンスをしやすくするために点検口の設置場所が指定されたりします。そのため、広大な吹き抜けや柱のない大空間など、自由で独創的な間取りやデザインが一部制限される場合があります。
長期優良住宅の申請プロセスと費用の目安

長期優良住宅の認定には、どのような手続きと費用が必要なのでしょうか。ここでは申請から認定までの流れを具体的に解説し、必要となる費用の相場もわかりやすくお伝えいたします。
【5ステップで解説】申請から認定までの流れ
【ステップ1】住宅の設計と計画
ハウスメーカーや工務店と相談し、長期優良住宅の認定基準を満たす設計図書と、将来のメンテナンス計画である「維持保全計画」を作成します。
【ステップ2】登録住宅性能評価機関へ事前審査を依頼
設計図書などが基準に適合しているか、専門の第三者機関(登録住宅性能評価機関)に技術的な審査を依頼し、「適合証」などを取得します。
【ステップ3】所管行政庁へ認定を申請
建築工事の着工前に、市区町村などの所管行政庁へ、ステップ2で取得した「適合証」などを添付して認定申請を行います。
【ステップ4】認定通知書の交付と工事着工
行政庁の審査を経て、基準に適合していると認められると「認定通知書」が交付されます。この通知を受けてから、建築工事を開始できます。
【ステップ5】工事完了と維持保全の開始
住宅が完成したら、工事完了の報告を行います。その後は、維持保全計画に沿った点検・修繕を開始し、その記録を保管する義務が始まります
申請に必要な書類
長期優良住宅の認定申請は、建築工事の着工前に行う必要があります。手続きは専門的な知識が求められるため、通常は設計を依頼したハウスメーカーや工務店、設計事務所が申請手続きを代行します。必要書類には、「認定申請書」や「添付図書(主なもの)」、「技術的審査適合証」が申請に必要になります。
詳しくは、家づくりの依頼をしている住宅会社に確認をしましょう。
申請にかかる費用の相場は?
費用は、①評価機関への審査料、②行政庁への申請手数料、③書類作成の代行料で構成されます。住宅の規模や依頼先により変動しますが、これらの合計で20万円〜30万円程度が一般的な相場です。
長期優良住宅に関するよくある質問
長期優良住宅を検討する中で浮かぶ、ZEHとの違いや認定の必要性といった様々な疑問があります。ここでは、特に多くの方が抱く質問をピックアップし、Q&A形式でわかりやすくお答えいたします。
長期優良住宅とZEH住宅は、どちらがいいですか?
目的によります。
家の資産価値や耐震性、長く住み続けるための耐久性を重視するなら長期優良住宅、月々の光熱費削減や環境への配慮を最優先するならZEH住宅がおすすめです。両方の良さを求めるなら併用が最適です。
長期優良住宅とZEHは併用できますか?
はい、併用できます。
長期優良住宅の認定基準とZEHの認定基準を両方満たすことで、耐久性・耐震性と、高い省エネ・創エネ性能を兼ね備えた、より高性能で資産価値の高い住宅を建てることが可能です。
長期優良住宅の認定を受けていない家は大丈夫?
はい、基本的には大丈夫です。
認定がなくても安全性に問題のない家をハウスメーカーや工務店は対応しています。
ただし長期優良住宅は、基準をさらに上回る性能を持ち、将来の維持管理まで計画された住宅と言えます。
芦屋市近辺で注文住宅を建てるなら高翔!
芦屋市を中心に注文住宅の住宅づくりを手掛ける高翔では、住宅の専門家「ハウスソムリエ」たちが土地探しから建築設計、アフターサービスまで、確かな知識と技術でトータルコーディネートいたします。
まずは、長期優良住宅をご検討の方も理想や憧れをハウスソムリエに話してみてください。世界でただひとつ、あなたとご家族のための最高の住宅をつくります。